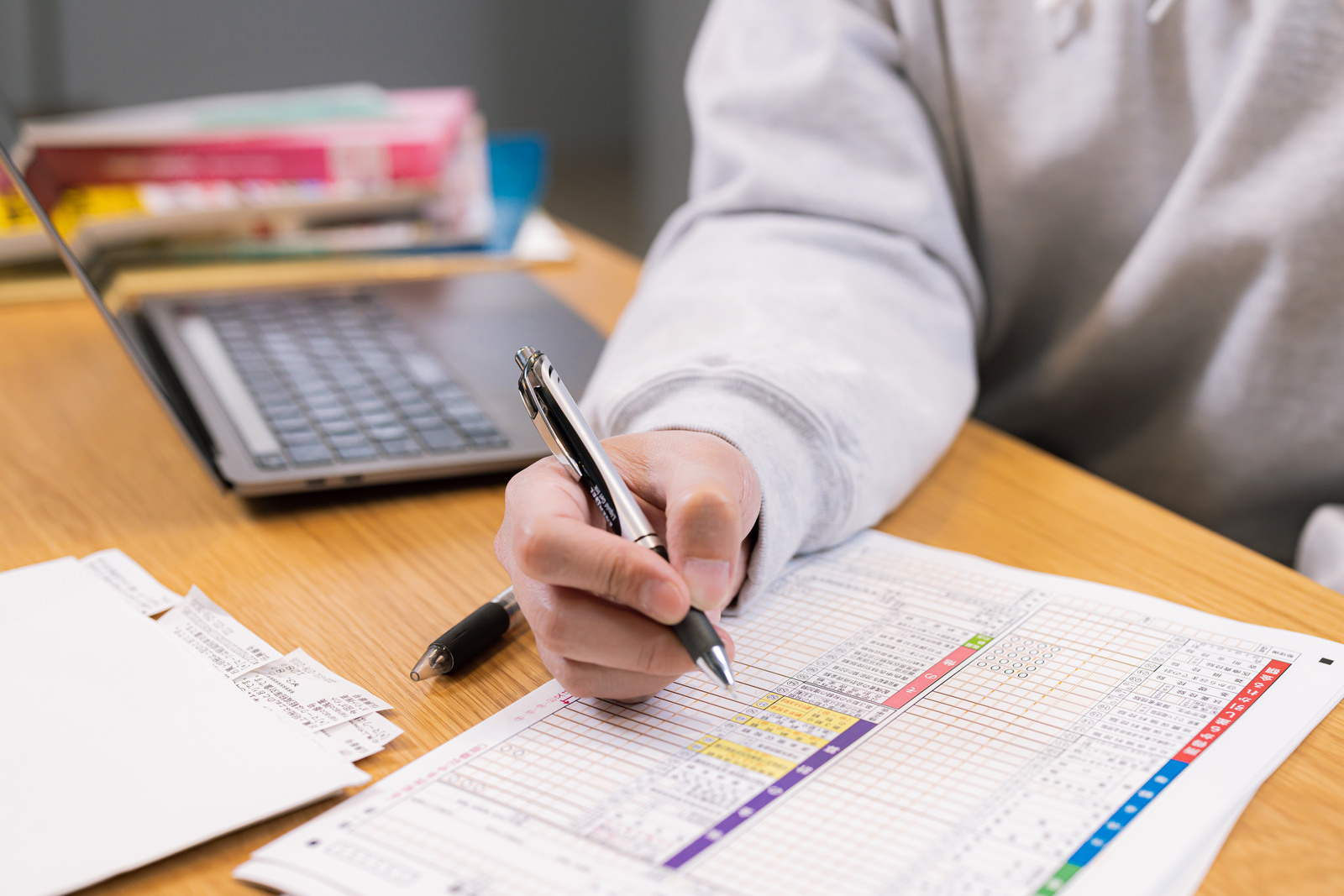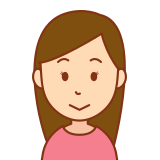
亡くなった父は自営業をしていました。
所得税の手続きはどうしたら良いですか?

ぶん太先生
4ヶ月以内に『準確定申告』という手続きをしましょう
相続手続きは、書類の収集や遺産の名義変更など、多数の手続きを行わなければなりません。
その手続きの一つに「準確定申告」があります。
これは、亡くなった方の所得に関する確定申告を相続人が代わりに行うもので、4ヶ月以内に行わなければなりません。
この記事では、準確定申告の流れや手続き方法について説明します。
準確定申告について
相続手続きの一環として行われる『準確定申告』は、亡くなった方(被相続人)の所得に関する確定申告を行うものです。
通常、確定申告はその年の収入に基づき翌年の3月15日までに行われますが、亡くなった場合、その年の1月1日から死亡日までの収入について相続人が申告する必要があります。

ふじの
本人が生きていたら行うはずだった確定申告の手続きをするということです。
準確定申告が必要な人
準確定申告が必要な場合
以下に当てはまる場合、準確定申告が必要となります。
- 亡くなった方が確定申告の対象者だった場合
- 個人事業主だった
- 不動産の家賃収入などの所得があった
- 会社員で年収2,000万円以上の収入があった
など
- 確定申告をしなければならない事情があった場合
- 不動産を売却した
- 株式を売却した
- 副業で20万円以上の収入があった
など
上記に当てはまらないが、控除・還付金が受けられる場合(申告は任意です)
- 多額の医療費を払っていた場合
- 給与所得者で源泉徴収が行われていない場合
- 配偶者控除、扶養控除の対象の場合
など
準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内です。
この期限内に申告書を作成して税務署に提出しなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があるため、早めの準備が重要です。
準確定申告の手続きの流れ

- 被相続人の収入・支出の把握
- 被相続人の収入や支出、控除額を正確に把握します。必要な書類を整理し、所得金額を算出します。被相続人の給与明細、事業所得に関する帳簿、不動産収入の明細、などを確認しましょう
- 提出書類の準備
税務署へ提出する書類は以下の通りです。- 確定申告書
- 確定申告書付表
- 亡くなった方の源泉徴収票
- 生命保険などの控除証明書
- 医療費等の領収書
- 委任状(代表相続人が還付金を受け取る場合)
- 申告書の作成・提出
- 所得税の申告書(確定申告書)を作成します。被相続人の所得金額や控除額を正確に記入し、計算ミスがないように注意します。
- 作成した申告書を、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。郵送や電子申告(e-Tax)も可能です。
- 準確定申告の納付
納付は以下の方法で行うことができます。- 税務署窓口
- 金融機関
- 口座振替
- クレジットカード
- e-Taxで納付
- インターネットバンキング
関連リンク

ふじの
準確定申告の手続きやに関連するサイトを掲載しますので、こちらもご参考ください。
確定申告書などの書類は、国税庁のページからダウンロードできます。
準確定申告の手続きについて(国税庁ホームページ)
おわりに
申告の内容や手続きには複雑な部分も多く、初めての方には難しく感じることもあるでしょう。
そのような場合には、無理をせずに税理士や税務署の相談窓口に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行うことができ、安心して相続を進めることができます。