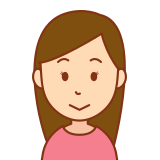
実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。
家財道具がたくさんあって、何から手を付けたら良いか…

まずは、遺言書があるか確認です。そして不動産の登記済証(権利証)や預金通帳など財産についての書類、さらに借用書やローンの郵便物など、借金についての書類を探してください。
相続が発生すると、まずは被相続人の財産調査が非常に重要になります。
相続手続きは、相続の開始と同時に速やかに始めることが求められます。
なぜなら、相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金も引き継ぐからです。
特に、相続放棄の手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、この期限を過ぎると放棄が認められなくなります。
この記事では、相続手続きの第一歩として重要な、借金と財産の調べ方について詳しくご紹介します。
正確な財産の把握と迅速な対応が、円滑な相続手続きを進めるための鍵となります。
借金・マイナスの財産の調べ方
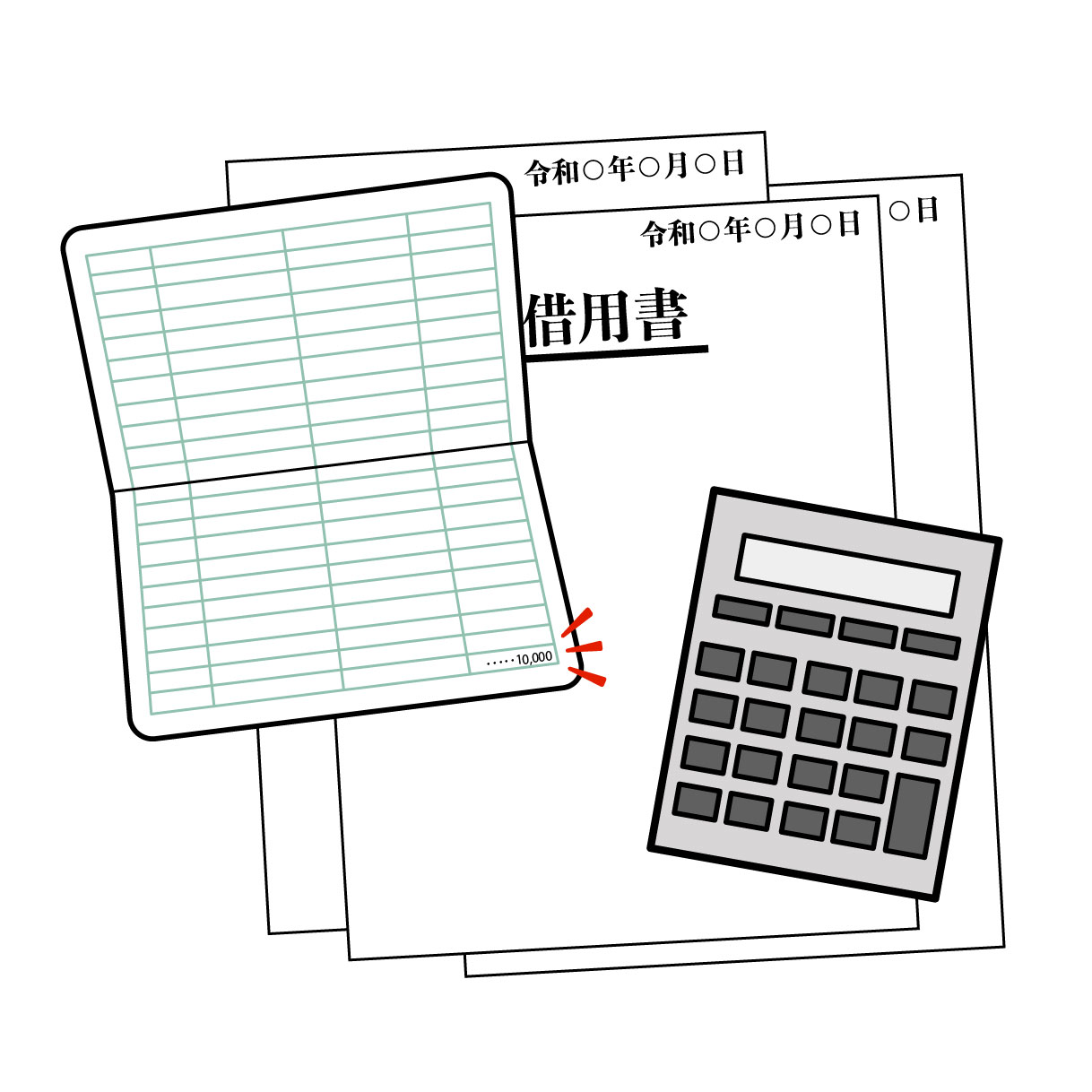
自宅内をよく調べる
被相続人の自宅内を徹底的に調べ、金銭の貸し借りに関する書類を探します
- 借用書や金銭消費貸借契約書:個人間で金銭の貸し借りをする際に作成されることが多い書類です。
- 手帳やノート:日記やメモ帳に借金に関する記録が書かれている場合があります。
- 通帳や振込明細:引き落とし記録や振込履歴から借入状況を確認します。
信用情報機関への照会
信用情報機関に対して情報開示請求を行うことで、被相続人の借金の詳細を確認できます。主な信用情報機関には以下の3つがあります。
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):銀行系の借金情報を調査できます。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカードや消費者ローンの情報を調査できます。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融などの借入情報を調査できます。
郵便物や留守電の確認
郵便物などにローンの督促状や請求書が届いていないか確認して未払いの請求がないかチェックします。また、被相続人の電話の留守電も確認し、金融機関からの督促の電話がないか確認します。
パソコンや携帯・スマホの確認
被相続人が利用していたパソコンや携帯電話を確認し、消費者金融やクレジットカード会社からのメールや、ブラウザのお気に入りに登録されている借入先の情報を探します。
発見しにくいマイナスの財産
1.個人間の借金
個人間の借金は信用情報機関等では調べることができません。
遺品から借用書などが見つからなくても相手が持っていることがあります。
また、生前返済されずに曖昧なままになっていたが、亡くなったことを知り相続人に催促に来るといったこともあります。
メールやLINE等の個人間のやり取りにお金の話がないか確認しましょう。
2.他人の借金の保証人になっている場合
被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、その負債も相続されます。他人の借金の保証人になっている事実を発見するのは難しい場合があります。
借りた本人が借金の返済が続けている間は、保証人には基本的に連絡が行きません。
借りた本人が返済できなくなった時に初めて保証人に連絡が来るため、後に保証人としての責任があることがわかる場合があります。
以下の方法で確認してください。
- 保証契約書の確認:保証契約書を見つけることで、被相続人が保証人となっている借金の詳細を把握できます。
- 信用情報機関への照会:金融機関からの借入の場合、信用情報機関に照会することで、被相続人が保証人となっている借金の情報も得られることがあります。
- 知人・親戚・友人に確認:被相続人が他人の借金の保証人になっていた可能性について、知人や親戚、交友関係の人々に聞き取りを行うことも有効です。特に、親しい友人や家族に尋ねることで、保証契約の存在や詳細を知る手がかりが得られる場合があります。
連帯保証人としての責任は主債務者と同等であり、主債務者が返済できなくなった場合には、連帯保証人がその借金を返済する義務を負います。このため、連帯保証人としての負債を見逃さないよう注意が必要です 。
プラスの相続財産の調べ方

預貯金の調査
- 銀行口座の確認:被相続人の全ての銀行口座を把握し、それぞれの口座から残高証明書を取得します。
- 取引履歴の確認:過去数年間の取引履歴を確認し、隠れた預貯金や出金の履歴をチェックします。
株式や証券の調査
- 証券会社への問い合わせ:被相続人が保有していた株式や証券について、各証券会社から残高証明書を取得します。
- 配当金の確認:配当金の支払い履歴も確認し、未払いの配当金がないか確認します。
不動産の調査
1.名寄帳を取得
名寄帳には、納税義務者が所有している不動産が一覧形式で記載されています。
市区町村役場の固定資産税課や税務課で取得することができます。取得には、申請書の提出とともに、相続関係を証明する戸籍謄本などの書類が必要になります。
2.登記事項証明書を取得
法務局で登記事項証明書を取得し、所在地と所有者の情報を特定します。
登記事項証明書には、抵当権(不動産を担保にお金を借りる)についての情報も書いてありますので確認しましょう。
不動産の価格について
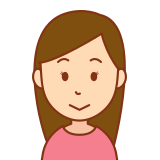
土地や建物はいくらで考えたら良いですか?

複数の不動産会社に査定書を作成してもらい、相続人同士で決めましょう。
遺産分割の場合は、不動産業者の査定を参照に
遺産分割は、相続人同士の話し合いで決めます。ですので全員が合意できるのであれば不動産の金額は柔軟に考えて問題ありません。
しかし、不動産を取得しない他の相続人から批判が出る場合もあります。
「固定資産税評価額」(固定資産税の計算のために各市町村が決めているしている額)は参考になりますが、市街地などでは市場価格とかけ離れていることが多いです。逆に地方の山林などの不動産は、市場価格はほぼゼロということもあります。
そのため、より現実的な価格を知るために、複数の不動産業者に査定書を作成してもらうことをお勧めします。こうして得られた査定額の平均を基に、相続人同士で話し合いましょう。
相続税申告の場合は、独自の計算方法で算出
相続税の申告の際は、査定額ではなく、国税庁で定められている路線価や固定資産税評価額を参照して算出します。
- 土地は国税庁が定める路線価評価方式、または倍率方式により計算
- 家屋は固定資産税評価額と同じ

相続税の申告の必要がある場合、評価額を正確に出さなければなりません。
難しい、面倒と思われる場合は、相続手続きに詳しい税理士さんに相談しましょう。
国税庁 財産評価基準のページ
財産調査前後の手続き
相続開始から、財産の調査のために必要な手続きをブログ記事にしています。
以下のリンクもご参考ください。
遺言書の確認
まず最初に行うべきことは、遺言書があるかどうかを確認することです。遺言書がある場合、それに従って財産を分けることになります。遺言書がない場合は、法定相続順位、または話し合いにより財産を分けます。
相続人の確定
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。これにより、すべての相続人を特定し、相続手続きの基礎を固めることができます。
相続放棄・限定承認の検討
相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを決定する必要があります。財産と負債のバランスを考慮し、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。
遺言の執行または遺産分割協議
遺言がある場合には、その内容に従って遺言執行者が遺産の分割を進めることが求められます。遺言執行者は、遺言に基づいて財産を管理し、遺言の内容を実現する役割を果たします。
遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。これにより、相続手続きが正式に完了し、各相続人がそれぞれの相続分を受け取ることができます。
おわりに
相続手続きにおいて、被相続人の財産や負債を正確に把握することは非常に重要です。
特に、マイナスの財産である借金などの負債は3ヶ月を過ぎると放棄できませんので、慎重に調査を行う必要があります。
プラスの財産についても、不動産や預貯金、株式などの詳細を把握することで、相続手続きを円滑に進めることができます。この記事を参考に、正確で迅速な相続手続きを心掛けてください。
必要に応じて専門家のサポートを受けることで、より安心して手続きを進めることができるでしょう。


