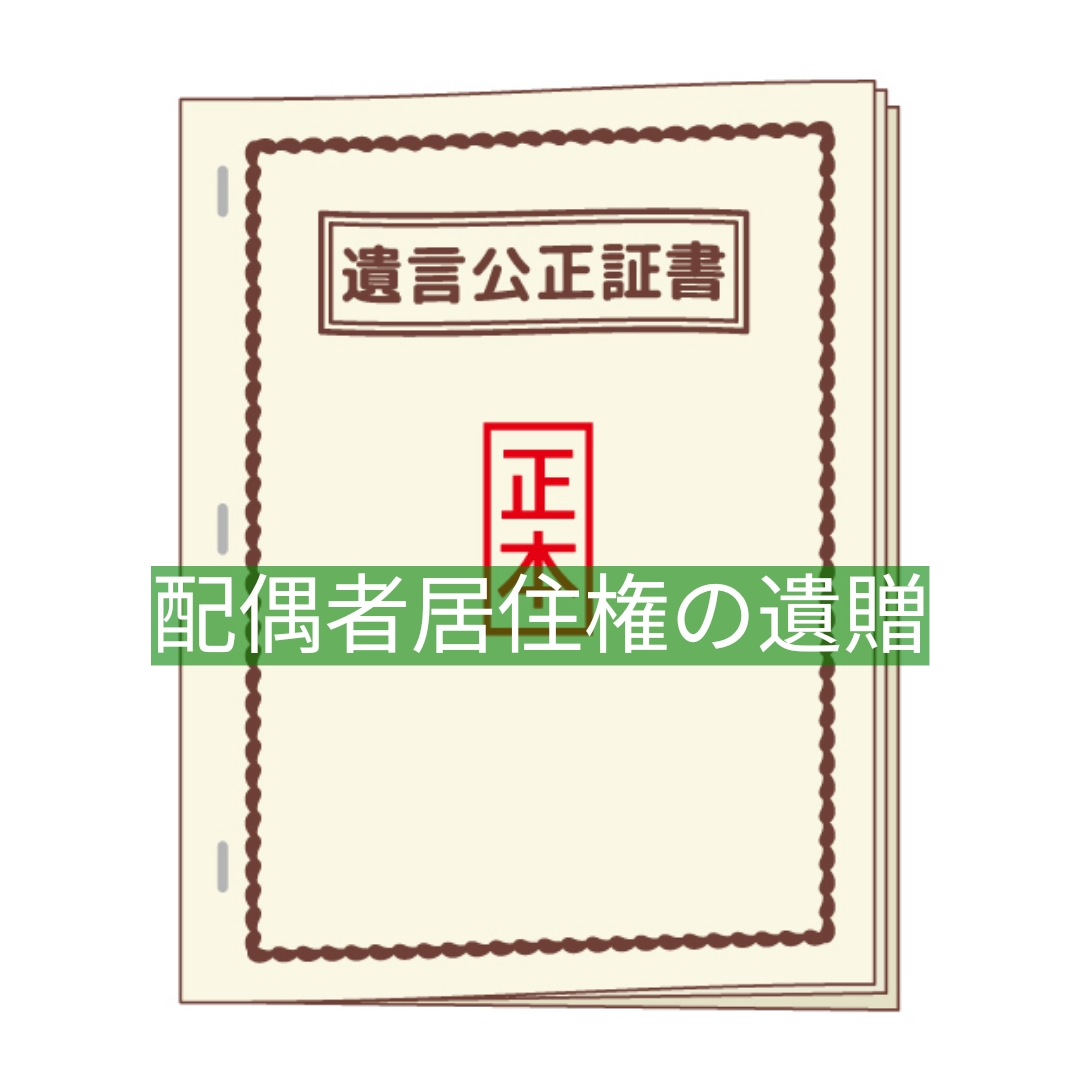私が死んだ後の相続が不安です。
財産は自宅とわずかな預貯金しかありません。妻が自宅を相続すると、子どもに公平に遺産を分けるのが難しくなりそうです。
妻には、住み慣れた家で安心して暮らしてほしいと思っています。

家の所有権を子どもに相続させて、妻には「配偶者居住権を遺贈」する方法があります。遺言書の作成を検討しましょう
配偶者が自宅に住み続けるための権利として、「配偶者居住権」という制度があります。これは、配偶者が安心して生活を続けるための重要な仕組みです。
配偶者であれば、土地家屋の所有権を相続しなくても、住み続けられる制度が設けられています。
本記事では、この配偶者居住権の概要、成立条件、そして遺言でこの権利を遺贈する方法について解説します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、家の持ち主である夫が亡くなった場合、配偶者である妻が生涯または一定期間、無償でその自宅に住み続けられる権利を指します。この権利は、被相続人(亡くなった方)の遺言による遺贈、または相続人同士の遺産分割協議によって成立します。
例えば、夫が所有する家に住んでいた妻が、夫の死後もその家に住み続けられるようにするためには、この配偶者居住権の制度を利用することが有効です。これにより、家を失う心配なく安心して暮らせるようになります。
配偶者居住権のメリット

①住み慣れた自宅に無償で住み続けられる:配偶者居住権を取得することで、残された配偶者は自宅の所有権を持たなくても、無償で終身その家に住み続けることができます。
②生活資金の確保が容易になる:自宅の所有権と居住権を分けることで、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産も相続しやすくなります。これにより、生活資金を確保しやすくなります。
③代償金の支払い負担を軽減できる:自宅の評価額が高く、配偶者がその所有権を相続すると他の相続人に対して代償金を支払う必要が生じる場合でも、配偶者居住権を活用することで、代償金の支払い負担を軽減できます。
配偶者居住権が成立する条件
配偶者居住権が成立するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者が相続開始時にその家に住んでいたこと
配偶者居住権は、相続が始まる時点でその家に実際に住んでいる配偶者に限られます。 - その建物が被相続人の単独所有、または配偶者と共有のものであること
配偶者居住権が成立する家は、被相続人の単独所有であるか、配偶者との共有である必要があります。 - 配偶者居住権が遺贈または遺産分割協議で決定されていること
遺言書での指定や、相続人同士の協議によって配偶者居住権が成立します。
遺言書で配偶者居住権を遺贈する
遺言書で配偶者居住権を遺贈することは、配偶者にとって非常に有効な方法です。以下に具体例を挙げます。
配偶者居住権の遺贈の例文
第◯条 遺言者 藤野太郎は、所有する自宅である下記建物の配偶者居住権を、
妻藤野花子(昭和〇〇年◯月◯日生)に遺贈する。
所 在 深谷市〇〇一丁目00番地0
家屋番号 00番0
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建
床 面 積 1階 00.00平方メートル
2階 00.00平方メートル
(※不動産の登記事項証明書の通り正確に記載します)
2 前項の配偶者居住権の存続期間は、妻花子の死亡の時までとする。
このように具体的な不動産を指定して配偶者居住権を遺贈することで、配偶者が安心して住み続けることができます。

「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します
おわりに
配偶者居住権は、高齢の配偶者が住む家を失うリスクを防ぎ、安心して暮らせる環境を整えるための重要な制度です。遺言書でこの権利を明確に遺贈することで、相続時のトラブルを防ぎ、配偶者を守ることができます。
相続や遺言についてお悩みの方は、専門家への相談をおすすめします。当事務所では、遺言書の作成サポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。