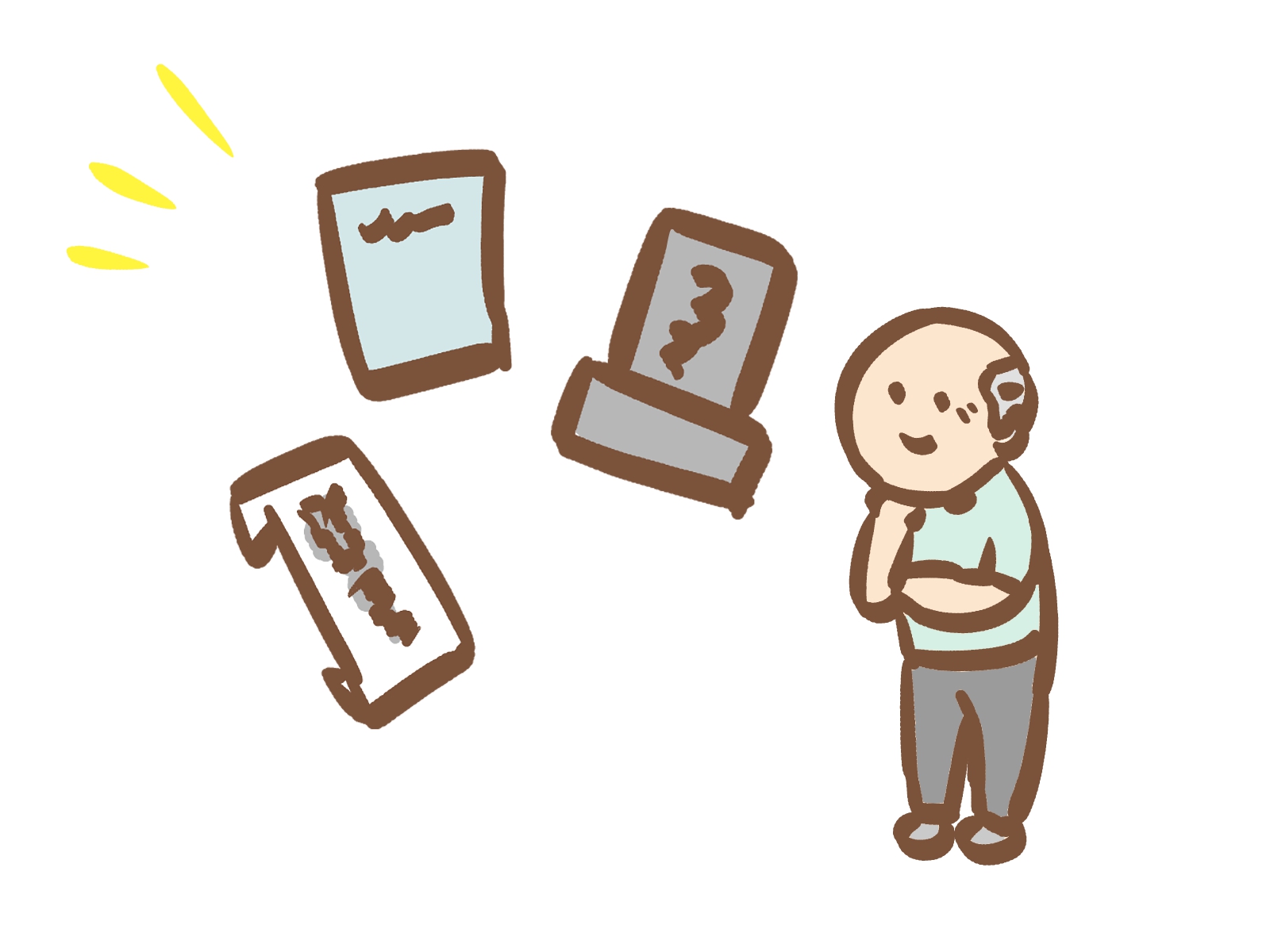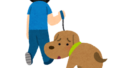近年、単身者や独身者の割合が増え、いわゆる「おひとりさま」の終活を検討する事例が増えています。家族がいない、または疎遠な相続人しかいない場合、何も対策をしないと財産の行方が不明確になり、最終的に国庫へ帰属する可能性もあります。
そのため、単身者や独身者こそ、生前の対策をしっかりと行い、自分の意思に沿った財産の管理や承継を考えておくことが重要です。本記事では、終活における重要なポイントを解説し、具体的な対策方法について詳しく紹介します。
生前に検討すべきこと
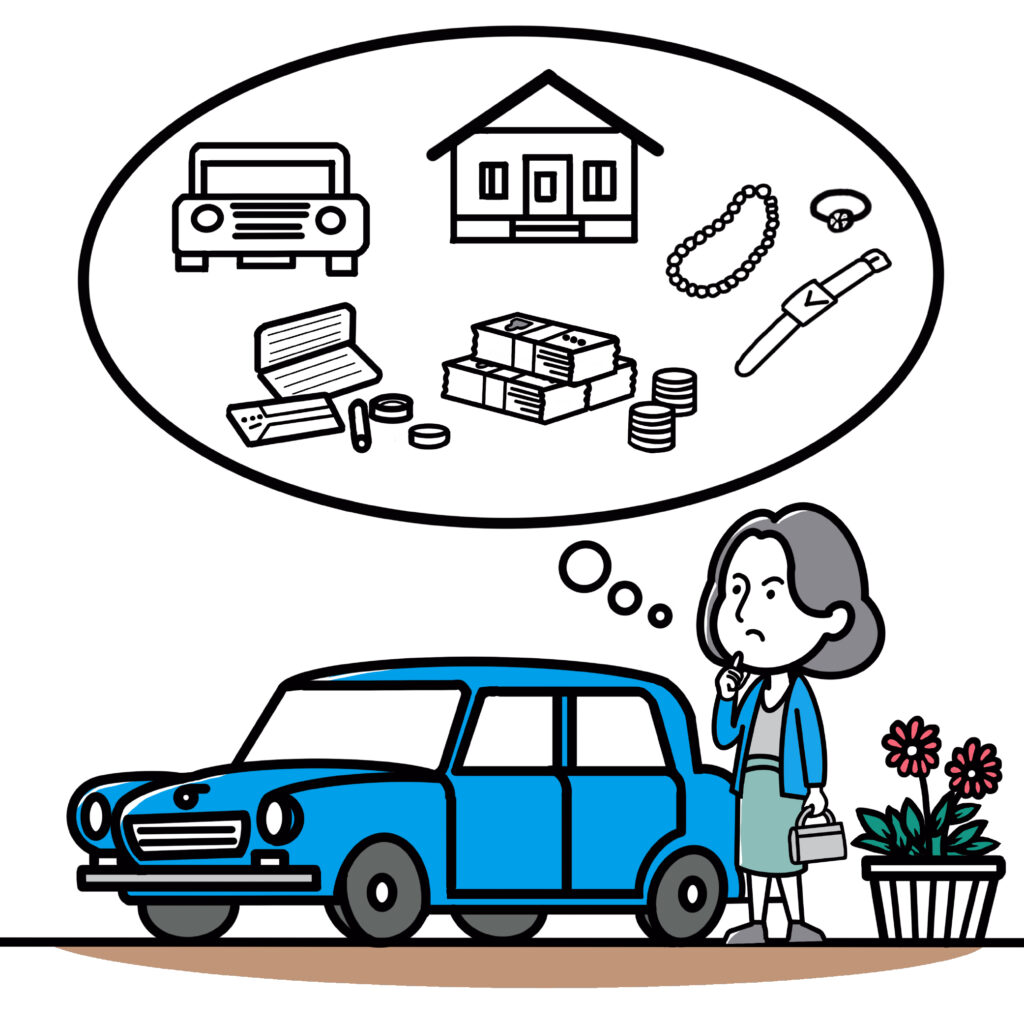
1. 推定相続人の調査
まず、あなたの財産を誰が相続することになるのかを確認することが重要です。民法では、法定相続人の順位が決められており、以下のようになります。
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:親(親が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
単身者や独身者の場合、第2順位(親)または第3順位(兄弟姉妹)が相続人になります。
親も兄弟姉妹もいない場合、相続人不在となり、最終的には国庫に財産が帰属することになります。
これを防ぐためには、遺言書を作成し、あなたの財産を受け取る人や団体を決めておくことが必要です。
推定相続人の調査の方法
相続人の調査は、あなたの戸籍を、生まれたときまで遡って取得します。
両親が離婚、再婚をしている場合で、父違い・母違いの兄弟姉妹がいる場合はその兄弟も相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子(あなたの甥、姪)が相続人になります。
2. 生前契約の検討
単身者や独身者は、家族がいる人に比べて、判断能力が低下したときや死亡後に支援をしてくれる人が少ないため、生前にさまざまな契約を結んでおくことが重要です。
親戚などに頼れる人がいない場合は、行政書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
特に検討すべき契約には、以下のようなものがあります。
- 見守り契約
定期的な安否確認をしてもらう契約で、高齢者の一人暮らしにおいて特に有効です。訪問型や電話・メールによる見守りサービスがあり、自治体や民間団体(社会福祉協議会など)が提供しています。 - 任意後見契約
判断能力が低下した際に、自分に代わって財産管理や生活上の支援を行ってもらう契約です。任意後見人には信頼できる人を選び、公正証書で契約を結ぶことで、いざという時に確実に支援してもらえます。 - 死後事務委任契約
葬儀や埋葬、遺品整理、各種解約手続き(公共料金・年金・保険など)を第三者に依頼する契約です。家族がいない場合、死亡後の事務処理をしてくれる人がいないため、信頼できる人や法人、行政書士や弁護士などに事前に依頼しておくことが重要です。
3. 遺言による財産の継承
単身者や独身者が財産を希望通りに分配するためには、遺言を作成しておくことが必須です。遺言書がない場合、法定相続人がいる場合は民法の規定に従って相続が行われ、相続人がいない場合は最終的に国庫に帰属することになります。
遺言にはいくつかの種類がありますが、主に以下の2つが一般的です。
- 自筆証書遺言
本人が全文を自筆で書く方式です。費用がかからず手軽に作成できますが、法的要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。 - 公正証書遺言
公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する方式で、法的に確実で、無効になるリスクがほとんどありません。費用はかかりますが、遺言執行者の指定もできるため、単身者や独身者にとっては特に安心できる方法です。
また、遺言の内容を確実に実行するために「遺言執行者」を指定しておきましょう。遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことで、信頼できる親族や専門家(行政書士、弁護士など)に依頼することができます。
このように、単身者や独身者が自分の意思を実現し、望まない結果を避けるためには、生前からの準備が非常に重要になります。
遺言書による対策・個別の事例

単身者や独身者の終活では、自分の状況に応じた対策を取ることが重要です。以下に、代表的なケースごとに具体的な対策を詳しく説明します。
1. 相続人がいない場合
遺言を書かないと財産が国庫に帰属します
単身者・独身者の中には、両親も兄弟姉妹もいない、またはすでに亡くなっているという方もいます。この場合、法定相続人がいないため、遺言がなければ財産は最終的に国庫に帰属することになります。
対策
- 財産の行き先を決める
自分が築いた財産を国に渡したくない場合、遺言を作成し、財産の分配先を明確に指定する必要があります。 - お世話になった人や団体への遺贈
長年親しくしていた友人、親戚、またはお世話になっていた企業・団体に財産を残すことができます。さらに、社会貢献を目的として、慈善団体(NPO法人・福祉団体・動物保護団体など)に寄付することも可能です。 - 公正証書遺言の活用
遺言が無効になることを防ぐため、公正証書遺言を作成するのが望ましいです。また、遺言執行者(弁護士・行政書士など)を指定することで、財産の適切な分配を確実に行うことができます。
2. 兄弟姉妹が相続人となる場合
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で自由に決められる
法定相続人が兄弟姉妹の場合、遺留分(最低限の相続分)がないため、遺言によって財産を自由に分配することができます。
対策
- 兄弟姉妹に相続させる場合
- 遺言がなくても兄弟姉妹は法定相続人なので、法定相続分に従って財産を受け継ぎます。
- 兄弟姉妹間でトラブルを避けるため、遺言で明確に分配を決めておくことが望ましいです。
- 甥や姪に財産を渡したい場合
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
- 存命の兄弟姉妹の甥や姪に直接財産を残したい場合は、遺言で明記する必要があります(遺言がないと相続権がないため)。
- 「〇〇(甥・姪)に全財産を遺贈する」と公正証書遺言に記載しておくと確実です。
- 兄弟姉妹以外に財産を渡したい場合
- 例えば、長年の友人やお世話になっている人がいる場合、遺言で指定しない限り、その人には財産が渡りません。
3. 疎遠な相続人(配偶者、子)がいる場合
遺留分に注意が必要
戸籍上の婚姻関係でも長年別居している場合や、子どもと疎遠になっている場合もあります。このようなケースでは、相続時にトラブルが起こりやすくなります。
対策
- 遺留分の把握
- 配偶者や子どもには遺留分(最低限の相続分)が認められています。
- 遺言で「すべての財産を〇〇に譲る」と書いたとしても、相続人が遺留分侵害額請求をすれば、法律上認められた最低限の相続分を請求できます。
- 遺留分を侵害しない遺言の作成
- 例えば、配偶者と疎遠になっていて、財産をすべて第三者に渡したい場合、遺留分に配慮した遺言書を作成することが重要です。
4. 事実婚・内縁関係のパートナーがいる場合
法的には結婚していないが、長年連れ添っているパートナーがいる場合、相続の問題が発生します。内縁関係では相続権がないため、遺言がなければパートナーは財産を受け取れません。
対策
- 遺言による遺贈
内縁関係の相手に財産を残したい場合、遺言で明記することが必要です。 - 生命保険の活用
生命保険の受取人にパートナーを指定することで、確実に財産を渡すことができます(生命保険金は遺産分割協議の対象外)。 - 公正証書遺言の作成
自筆証書遺言は紛失や無効になるリスクがあるため、公証役場で公正証書遺言を作成するのが確実です。
おわりに
単身者や独身者の終活では、「誰に財産を残すのか」「判断能力が低下した際にどうするのか」「死後の手続きを誰に依頼するのか」といった問題を事前に考えておくことが大切です。
遺言や生前契約を活用することで、望まない財産の分配を防ぎ、信頼できる人や団体に財産を託すことができます。特に、公正証書遺言や任意後見契約、死後事務委任契約などを活用すれば、将来のトラブルを回避し、安心して生活することができるでしょう。
早めの準備が、安心した未来につながります。ぜひ、この記事を参考に、自分に合った終活の方法を検討してみてください。