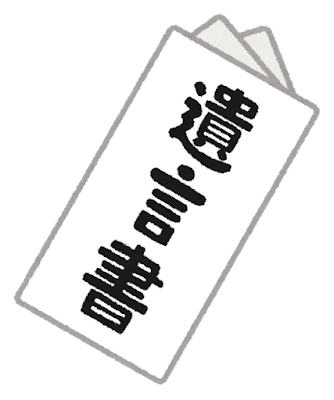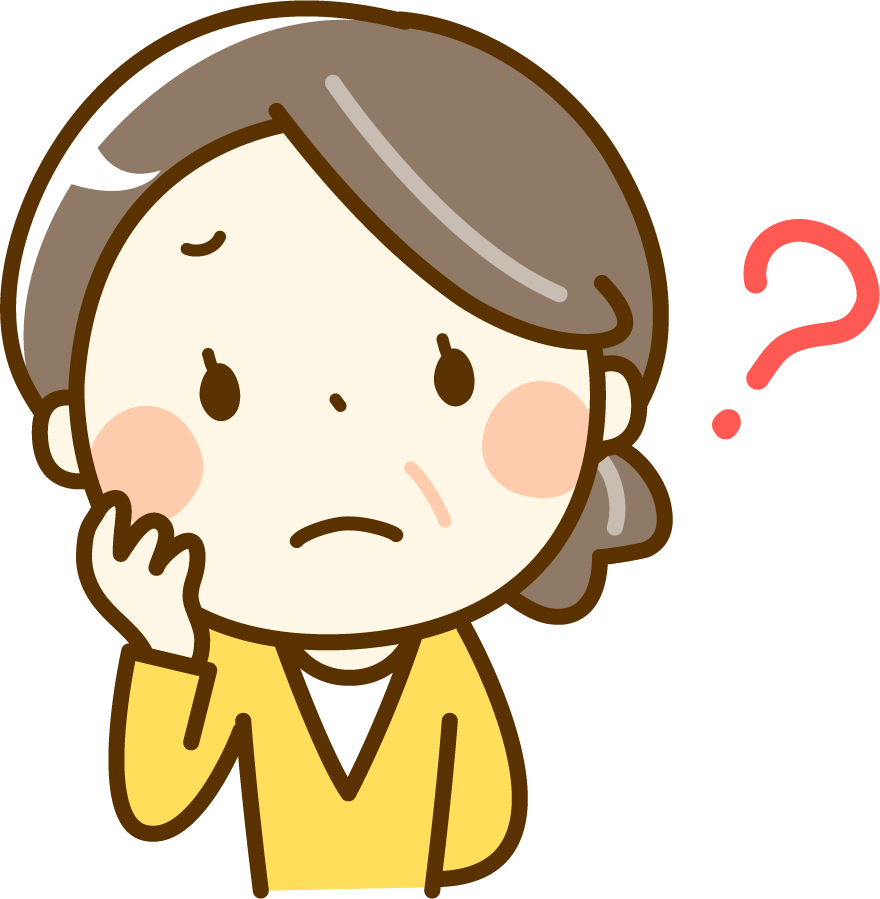
私の預貯金などの財産は娘にあげたいです。
遺言書を書いておけばすべて娘のものになりますよね?。

他の相続人に、『遺留分(いりゅうぶん)』という最低限の取り分があります。
それを踏まえて検討しましょう。
相続人には、法律で定められた最低額の取り分である『遺留分(いりゅうぶん)』があります。遺留分は、相続人が一定の割合を受け取れるように保護する制度です。
この記事では、遺留分についての解説や、遺言作成時の注意点などを解説します。
《ご相談の事例》
ご相談者様 女性 預貯金と土地を所有
推定相続人 夫と子(娘)一人
夫婦関係の事情により、夫に遺産を渡さずすべて娘に相続させたい。
遺留分について
遺留分とは
遺留分とは、特定の家族(相続人)が最低限受け取ることが保証されている相続財産の割合のことです。
例えば、亡くなった人(被相続人)は遺言によって自分の財産を自由に誰かに渡すことができますが、それを完全に自由にしてしまうと、家族が生活に困ることもあります。
そのため、法律では特定の相続人が必ず受け取れる財産の一部が決められています。
それを受け取るかどうかは、その相続人が自分で決めることができます。
遺留分を請求できる人
遺留分を受け取る権利があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条)。
また、胎児も相続に関してはすでに生まれているとみなされるため、遺留分を受け取る権利があります(民法886条)。
しかし、相続人であっても、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失った人は、遺留分を受け取る権利がありません。
ただし、相続欠格や廃除の場合、その人の代わりに相続する代襲相続人や、次の順位の相続人がいる場合は、その人が遺留分を受け取る権利を持ちます(民法1044条、887条2・3項)。
遺留分の割合
遺留分は、相続人が直系尊属(例えば親)だけの場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の相続人がいる場合は財産の2分の1が基準になります(民法1042条)。
遺留分を受け取る人が1人だけなら、その人がその全額を受け取ります。
もし複数の遺留分権利者がいる場合は、全体の遺留分が法定相続分に応じて各人に分けられます。
遺留分=法定相続分の1/2
この記事のご相談の事例の場合、
法定相続分 夫 1/2 娘 1/2
夫の遺留分 1/2 × 1/2 = 1/4の遺留分があります。
すべて相続させる遺言は書ける?
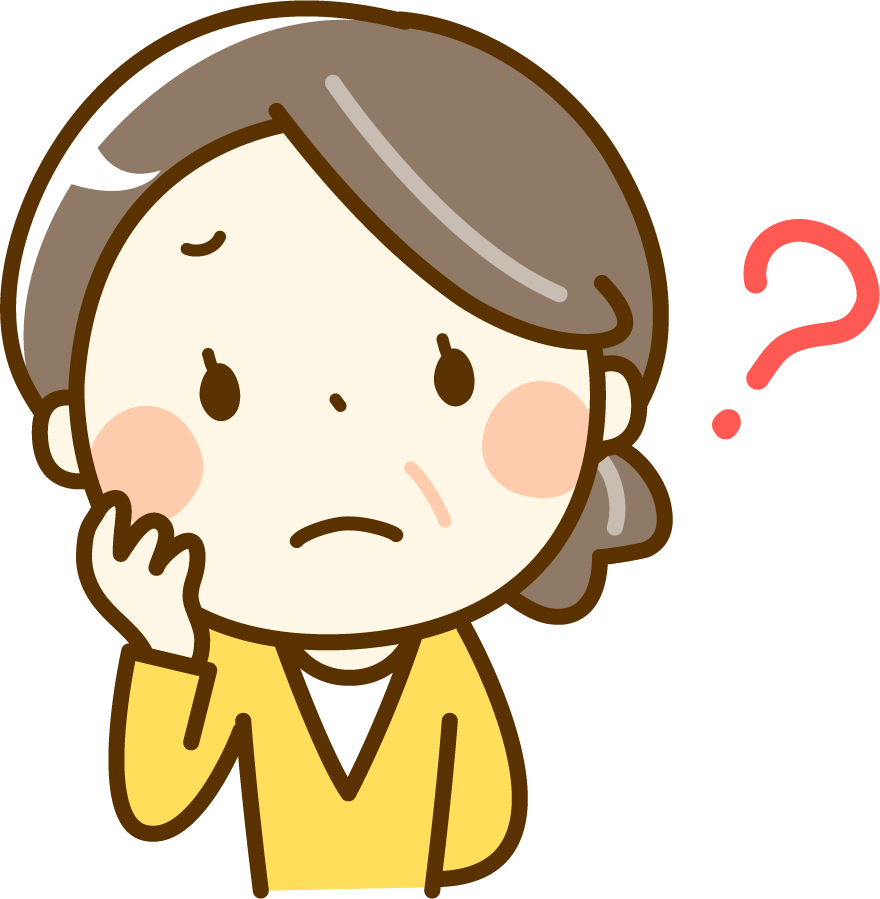
では、すべて相続させるという遺言は書いても無効になってしまうのですか?

すべて相続させる遺言も有効です。
遺留分を侵害していても遺言書そのものは無効になりません

でも、遺留分を請求されたら支払わなければなりません
遺留分を侵害する遺言書については、遺言そのものが無効になるわけではありません。
しかし、遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は侵害された分を他の相続人や受遺者から金銭で請求する権利があります。
遺留分の権利を持つ相続人から「遺留分侵害額請求」をされた場合、相続人や受遺者はその請求に応じて、遺留分を支払う義務があります。
したがって、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合でも、その遺言自体は無効とはなりませんが、遺留分権利者の請求を受けた場合には、その金額を支払わなければならないという点を理解しておくことが重要です。
遺留分対策と注意点
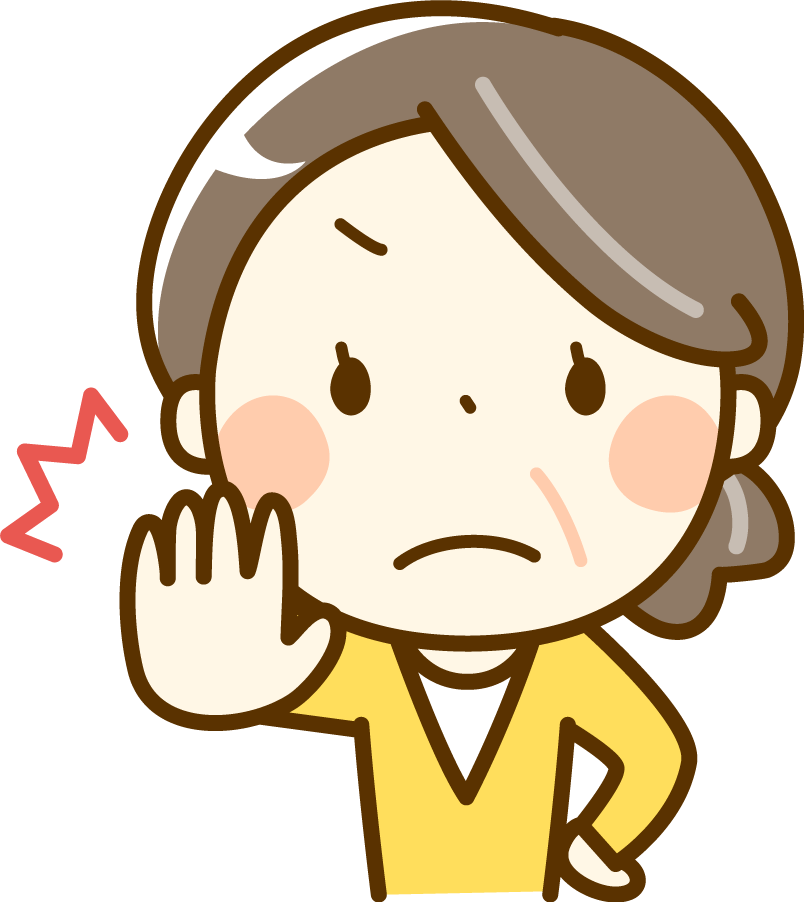
それなら、私が死ぬ前に全部娘に贈与しちゃいます!
夫には一円も渡したくないです!

生前贈与は遺留分を減らすために有効な方法ではあります。
しかし、色々と注意点があります。
財産を減らす、相続人を増やすことで、他の相続人の遺留分を減らすことは可能です。
遺留分対策1. 養子縁組を利用する
養子縁組を活用することで、遺留分を減らすことが可能です。具体的には、養子を迎えることで相続人の数を増やし、遺留分の割合を下げることができるからです。法定相続人の数が増えると、遺留分を主張できる相続人一人当たりの取り分が減少します。
ただし、遺留分の減少を目的とした養子縁組はその有効性を争われる可能性があります。
遺留分対策2.生命保険を活用する
遺産の一部を生命保険に変えることで、相続財産を減少させ、遺留分を減らす方法です。
生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産として扱われ、相続財産には含まれません。そのため、遺留分侵害額請求の対象外となります。
例えば、現金をそのまま遺産として残すのではなく、一時払い(保険料一括払い)終身型生命保険に加入し、その受取人を信頼できる相続人に指定することで、遺産総額を減少させることができます。
ただし、生命保険金が過度に高額である場合、特別受益とみなされ、遺留分の計算に含まれる可能性があります。
遺留分対策3.生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に相続人や第三者に財産を贈与することで、相続時の財産を減らす対策です。生前に財産を減らすことで、相続時に残る財産が少なくなり、結果として遺留分の対象となる財産も減少します。
生前贈与の注意点① 一定期間内の贈与額は戻して計算する
相続人以外の人への贈与の持戻し
- 原則として、相続が始まる前の1年間に行われた贈与が対象となります(民法1044条1項前段)。
相続人に対する贈与の持戻し
- 相続が始まる前の10年間に行われた贈与が対象となります(民法1044条3項)。
遺留分計算の基本となる財産の額
相続開始時の財産 + 贈与額( 相続開始前1年または10年の贈与額)− 相続した債務
生前贈与の注意点②過去の贈与の全額が持ち戻しになることも
当事者双方(この記事の事例では母と娘)が遺留分権利者に損害を加えることを知っていながら贈与を行ったと認められると、その贈与分を全額戻した額で計算することになります。
遺留分侵害額請求の消滅時効
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、以下の二つの期間のいずれかが満了した時点で成立します。
- 遺留分権者が遺留分が侵害されたことを知った時から1年
- 相続開始(被相続人の死亡)から10年
遺留分侵害額請求をされないための方法
1. 遺留分放棄
遺留分放棄とは、相続人が自らの遺留分を放棄することです。これは、相続人の意思によるものであり、放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分放棄の手続きは、生前に行う必要があります。遺留分放棄が認められれば、その相続人は遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。

遺留分放棄を裁判所に認めてもらうには、本人の意志によること、相当の対価を受け取っていることなどが必要です。(すでに遺留分相当額の贈与を受けているなど)
2. 相続人廃除
相続人廃除は、相続人が故人に対して『虐待、重大な侮辱、著しい非行』を行っていた場合に、故人がそのものを推定相続人から廃除する手続きです。
相続人廃除の手続きは、遺言書で指定するか、生前に家庭裁判所に申立てを行うことで実行されます。廃除が認められれば、その相続人は遺留分を含むすべての相続権を失い、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
相続人の行動が『虐待、重大な侮辱、著しい非行』にあたるかは裁判所が判断します。遺言書に「廃除する」と書くだけでは効果はありません。
相続人廃除は、厳格に審査、判断されます。単なる不和や些細な争いは廃除の理由として認められません。
相続人廃除が認められるケースは限られており、実際にはなかなか認められないのが現状です。

廃除が認められるのは、申立ての2割程度だと言われています。
3. 離婚
婚姻関係にある配偶者は法定相続人であり、遺留分を有しますが、離婚すればその配偶者は相続権を失います。これにより、元配偶者が遺留分侵害額請求をすることはなくなります。ただし、離婚には当然ながら夫婦関係の破綻が前提となります。
様々な事情を考慮してご判断ください
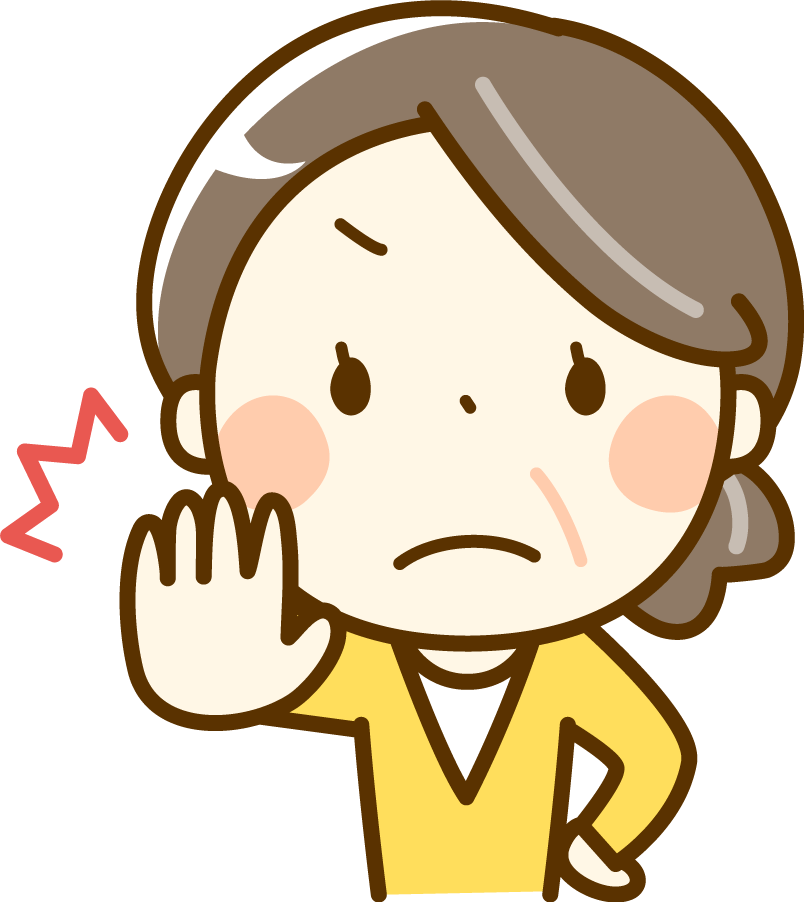
夫には全部娘に渡すと言ってあるし、娘を相手に裁判なんかするわけないです。

財産の額や、事情、相続人になる方の人間関係などを考慮して、最終的にご自身でご判断ください。
遺言で遺留分を侵害する場合、いくつかの重要な注意点を考慮する必要があります。
まず、財産の額が遺留分を大きく左右します。遺留分は、相続財産の一定割合を保証する法定の権利です。遺言で特定の相続人や第三者に財産を多く残したいと考えている場合、その金額が他の相続人の遺留分を侵害しないか慎重に確認することが必要です。遺留分を無視した遺言は、後々トラブルや遺留分侵害額請求を招く可能性があるため、財産の全体的な価値と分配のバランスを見極めることが大切です。
次に、遺言を書く事情も重要なポイントです。たとえば、ある相続人に特別な世話をしてもらったため多く財産を残したいという場合、その理由を明確に説明することが望ましいです。また、他の相続人との関係が悪化している場合でも、遺留分は法定権利として保護されているため、無視はできません。理由を明示することが、後々の争いを防ぐ一助となるかもしれません。
推定相続人の人間関係も、遺言内容を決定する上で大きな影響を与えます。相続人間に感情的な対立や緊張がある場合、遺言によってそれが悪化する可能性があります。財産の公平な分配を考えることで、相続時の対立を緩和できる場合があります。また、遺言を作成する際には、相続人が遺留分侵害額請求を起こさないための対策(例:生前贈与や遺留分放棄の交渉)も検討する価値があります。
最終的には、これらの要素を総合的に判断し、ご自身の望む財産分配がトラブルに発展しないか、また円満な相続が実現できるかどうかを慎重に考えることが大切です。