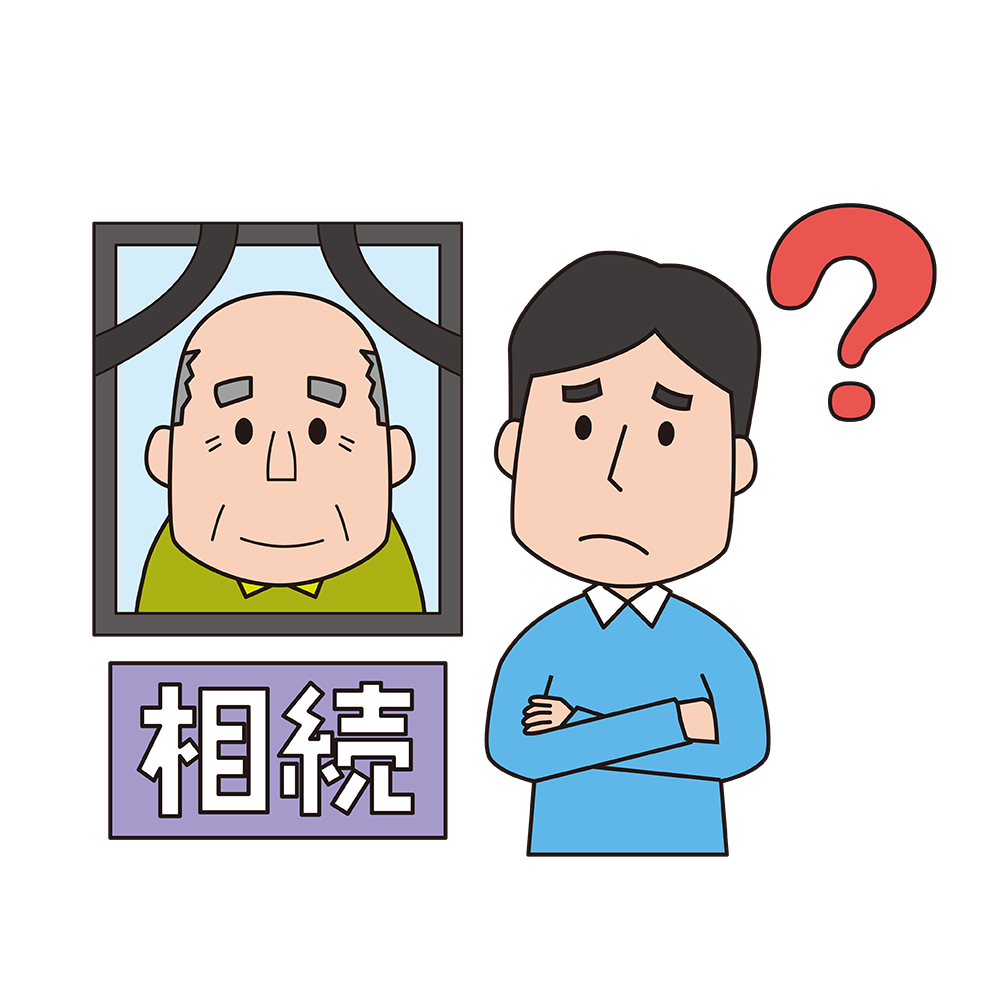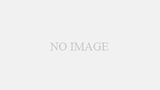「独身の叔父が亡くなったけど、相続手続きってどうすればいいの?」
「子どもも配偶者もいない兄の相続、私に関係あるの?」
こうしたご相談は、40~60代の方から多く寄せられます。
独身で亡くなった方の相続は、配偶者や子どもがいないために、誰が相続人になるのか分かりにくいのが特徴です。
また、子どもがいない方の相続はトラブルになりやすいので注意が必要です。
この記事では、独身者が亡くなった場合の相続人のルールや、手続きの進め方をわかりやすく解説します。
独身・おひとり様の相続人の順位と具体例
相続は、法律で定められた順位に従って、相続人が決まります。
第1順位:子どもや孫(直系卑属)
故人が結婚歴のある方で、前配偶者との間に子どもがいたり、未婚のパートナーとの間の子を認知している場合、その子どもが相続人となります。
その場合、親や兄弟姉妹ではなく、その子がすべての財産を相続します。

子どもがすでに亡くなっている場合は孫が相続します。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
第2順位:親や祖父母(直系尊属)
故人に子どもがいない場合、親(父母)が相続人になります。
両親が存命であれば、財産を2分の1ずつ分けます。どちらかが亡くなっていれば、残った親が全額相続します。
両親ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人になることもあります。
第3順位:兄弟姉妹と甥・姪
親も子どももいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
もし兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている方がいれば、その方の子ども(つまり甥・姪)が相続人になります。(代襲相続(だいしゅうそうぞく))
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。

兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。甥・姪の子は相続できません。
相続人調査と相続手続きの流れ
相続手続きを進めるには、まず相続人を確定することが最重要です。
【基本的な流れ】
- 遺言書の有無を確認
- 故人の戸籍を出生から死亡まで取り寄せる
- 相続人を確定する(相続関係説明図の作成)
- 相続財産の調査(預貯金・不動産・債務など)
- 遺産分割協議書の作成(相続人が複数いる場合)
- 遺産の名義変更・解約手続きなどの実行
- 相続税の申告(必要な場合)

戸籍の収集や関係図の作成は、行政書士に依頼することでスムーズに進められます。
遺言書がある場合は内容が優先される
相続では、遺言書の内容が法律よりも優先されるのが原則です。
つまり、法定相続人の順位に関係なく、遺言で「この人に財産をすべて渡す」と書かれていれば、その内容が基本的に尊重されます。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言:本人が手書きで作成。開封には家庭裁判所での「検認」が必要。
- 公正証書遺言:公証人の立会いで作成。安全性が高く、検認が不要。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証役場で手続きを行う。利用は少ない。
※相続手続きにおいて遺言書が見つかった場合は、その取り扱いに注意が必要です。
遺言があっても「遺留分」に注意が必要
遺言書があっても、すべてがそのまま実現されるとは限らない場合があります。
なぜなら、一部の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の相続の取り分が、法律で保障されているからです。
遺留分が認められる相続人
- 子ども(または孫)
- 配偶者
- 親・祖父母(直系尊属)
🟡 兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹が相続人になるときはトラブルが起こりやすい?
独身の方の相続では、兄弟姉妹やその子(甥・姪)が相続人になるケースが多くあります。
しかしこの場合、相続人同士の関係性が希薄である場合もあることから、遺産分割協議がスムーズに進まないことも少なくありません。
よくあるトラブル例
- 長年介護していた兄弟が「自分が多くもらうべき」と主張
- 兄弟姉妹の中に連絡が取れない人がいて協議が進まない
- 異母兄弟、異父兄弟も相続人となり、お互いに面識がないため相手が対応してくれない
- 兄弟姉妹の配偶者が口を挟んで、話し合いが進まない
- 甥・姪が相続人になる場合、顔も知らない間柄で感情的な対立が生じる
✅ 対処法
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
合意できない場合は話し合いがまとまらない、あるいは連絡が取れない相続人がいる場合などは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停では、裁判所の調停委員が第三者として間に入り、各相続人の主張を整理しながら解決を目指します。