近年、法律婚にとらわれず、事実婚(内縁関係)を選ぶカップルが増えています。夫婦として日常生活を共にし、財産を築いているにもかかわらず、法律上は正式な夫婦とは認められず、相続の場面で大きな壁に直面することがあります。
もしパートナーが突然亡くなったら、あなたはその財産を相続できるでしょうか?
実は、事実婚の配偶者には法定相続権が認められていません。つまり、適切な対策をしていなければ、亡くなったパートナーの財産はすべて親族に渡り、事実婚のパートナーは何も受け取れない可能性があるのです。
しかし、事前にしっかりと準備をしておけば、事実婚のパートナーでも財産を受け取ることができます。本記事では、事実婚の相続問題とその対策について、具体的な方法を解説します。
事実婚のパートナーが亡くなったときの相続の現実
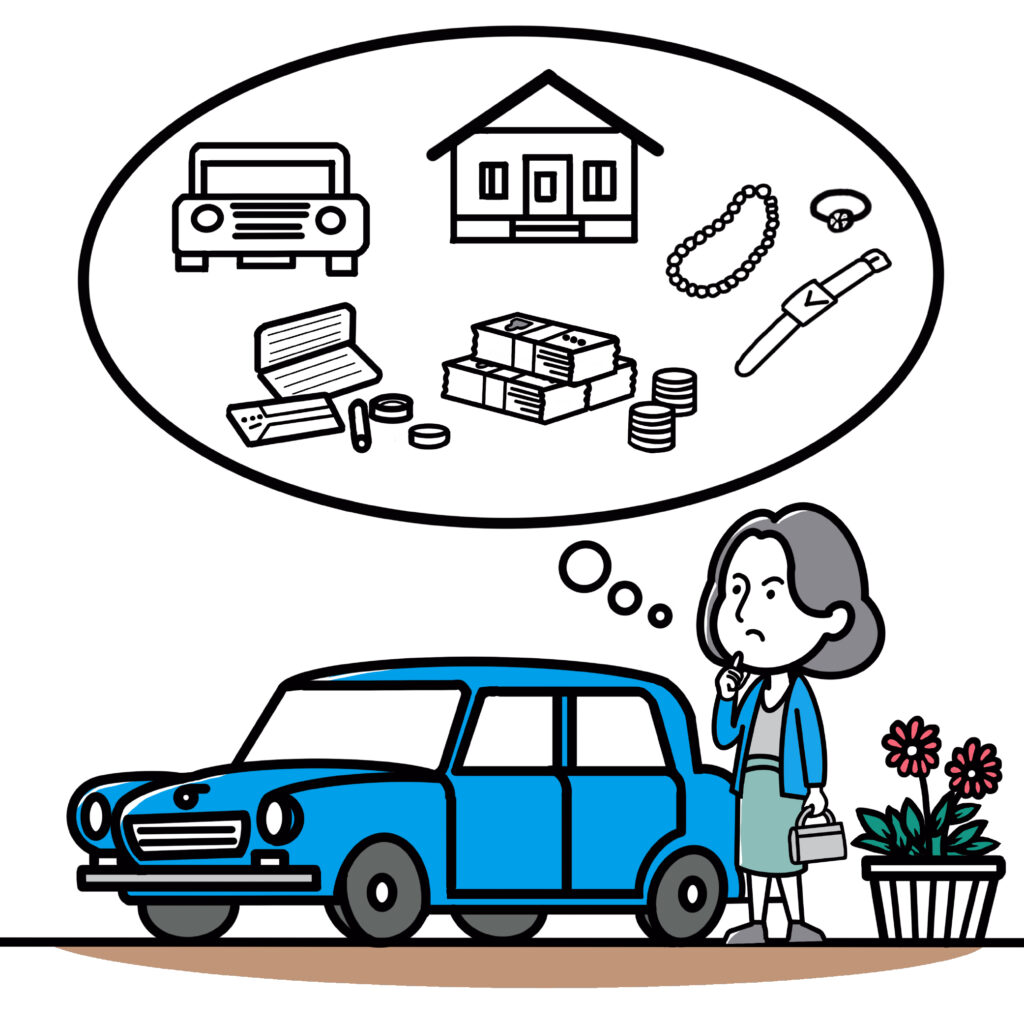
事実婚(内縁関係)のカップルは、長年ともに生活し、財産を築いてきたとしても、法律上の婚姻関係ではありません
もし、パートナーが遺言を残さずに亡くなってしまった場合、残された側は以下のような問題に直面する可能性があります。
1. 事実婚の配偶者は遺産を受け取れない
法定相続人として認められるのは以下の人々です。
- 常に相続人:法律上の婚姻関係の配偶者
- 第1順位:子ども(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
法律上の配偶者には常に相続権がありますが、事実婚のパートナーは法定相続人に含まれないため、一切の相続権を持ちません。 そのため、何の対策もしていない場合、亡くなったパートナーの財産は全て親族に渡ることになります。
2. 住んでいた家を追い出される可能性も
例えば、事実婚のパートナーと一緒に暮らしていた家の名義が亡くなった側のものであった場合、その財産は法定相続人に相続されます。
もし相続人が家を売却したり、明け渡しを求めたりした場合、残されたパートナーは住み続けることができなくなるかもしれません。
3. 預貯金の引き出しができない
故人の銀行口座は、死亡が確認されると凍結され、相続手続きが完了するまで引き出せなくなります。事実婚のパートナーには相続権がないため、単独で銀行口座の解約や引き出しはできません。
もし遺言書がなければ、亡くなったパートナーの親族と話し合いをしない限り、口座のお金を受け取ることができなくなります。
事実婚夫婦がとるべき相続対策

事実婚のパートナーには相続権がないため、何の対策もせずにいると、亡くなった際に財産を一切受け取れない可能性があります。しかし、適切な準備をしておけば、事実婚のパートナーでも財産を確実に受け取ることができます。ここでは、事実婚カップルがとるべき相続対策を具体的に紹介します。
(1) 遺言書を作成する
事実婚のパートナーに財産を確実に遺すためには、遺言書の作成が最も重要です。
遺言書を残しておけば、パートナーに財産を分配できるだけでなく、親族とのトラブルを防ぐ効果もあります。
遺言書の種類と選び方
遺言書にはいくつかの種類がありますが、確実に遺言の内容を実現するためには「公正証書遺言」がおすすめです。
| 遺言の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 法的に有効、紛失や改ざんのリスクなし | 費用がかかる(数万円~) |
| 自筆証書遺言 | 本人が手書きで作成 | 手軽に作成できる | 書式不備で無効になるリスク |
| 秘密証書遺言 | 本人が作成し、公証役場で証明手続き | 内容を秘密にできる | 手続きが複雑で、執行時に無効になる可能性あり |
公正証書遺言を作成することで、事実婚のパートナーに確実に財産を遺すことができます。
公正証書遺言を作成するメリット
公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するため、確実に法的効力を持ち、無効になるリスクがないのが最大のメリットです。
✅ 偽造・改ざん・紛失の心配がない(公証役場が保管)
✅ 確実にパートナーへ財産を遺せる(法的に有効な形で作成できる)
✅ 裁判所の検認手続きが不要(手続きがスムーズ・早い)
✅ 行政書士等の専門家に相談しながら最適な内容にできる
「遺留分」に注意しましょう
遺言によって事実婚のパートナーに財産を遺すことは可能ですが、法定相続人(子どもや親)には「遺留分」という最低限の権利があります。
全財産をパートナーに遺贈する遺言を書いても、全額パートナーが受け取ることはできない場合があります。
パートナーに、前配偶者との子、法律上の配偶者(離婚の手続きをしていない)、親がご存命、等の場合は遺留分を考慮した内容を検討しましょう。
📌 遺留分の割合
- 離婚していない法律上の配偶者がいる場合:配偶者の相続分の1/2が遺留分
- 子どもがいる場合:子の相続分の1/2が遺留分
- 親がいる場合:親の相続分の1/3が遺留分
- 兄弟姉妹には遺留分なし。相続人が兄弟姉妹のみなら、全額パートナーへ渡せます

法定相続人に遺留分を主張された場合、その額を金銭で支払わなければなりません。
後のトラブルの発生や、パートナーが精神的な負担を受けることになりますので、遺留分を侵害しない遺言書を作成しましょう。
(2) 生前贈与を活用する
事実婚のパートナーに財産を遺す方法として、生前贈与を活用するのも有効な手段の一つです。
生前に財産をパートナーへ贈与することで、遺産相続の対象となる財産を減らしつつ、パートナーに確実に財産を移転できます。
ただし、贈与には贈与税がかかる場合があるため、計画的に行うことが重要です。
贈与税の基礎控除
- 年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからない。
- 毎年110万円以内の贈与を続ければ、大きな財産も税負担なく移転できる。
注意点
- 相続時にまとめて税額を支払う相続時精算課税制度は適用されない(この制度は親子間のみ適用)。
- 贈与税の配偶者控除は適用されない(法律上の配偶者のみ適用)
- 長期的な贈与の計画が重要
- 毎年、同じ金額を同じ時期に贈与し続けると、税務署から一括贈与とみなされ贈与税が加算されることがあります。贈与の時期や金額に変化をつけるなど、適切な対策を講じることが重要です。
(3) 生命保険の活用
生命保険の死亡保険金は、相続財産とは別枠で受け取ることが可能です。遺言書がなくても、生命保険契約で受取人を事実婚のパートナーに指定しておけば、確実に財産を渡すことができます。
生命保険のメリット
- 遺言がない場合でもパートナーに確実に財産を遺せる。
- 保険金は相続財産ではなく、受取人固有の権利となる
- 銀行口座が凍結されても、保険金は迅速に支払われる。
注意点
- 保険会社によっては、事実婚のパートナーを受取人に指定できない場合がある、または事実婚を証明する書類を求められます。事前に確認が必要です。
事実婚を証明する書類の作成

事実婚(内縁関係)のパートナーとの暮らしや、各種手続きを行うためには、「事実婚であること」を証明することが重要です。
特に、保険の手続き、パートナーの入院・医療行為への同意、介護の申請手続きなどを行う際、婚姻関係を証明できないと手続きがスムーズに進まない場合があります。
ここでは、事実婚であることを証明するための具体的な方法を紹介します。
(1) 住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と記載する
住民票の続柄欄に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載することで、事実婚関係を公的に示すことができます。この手続きは、市区町村の役所で行います。手続きの際には、以下の点に注意してください。
- 条件:双方が法律上、他の者と婚姻関係になく、婚姻の意思を持ち共同生活を営んでいること。
- 手続き方法:役所の窓口で、世帯主を一方とし、もう一方の続柄を「夫(未届)」または「妻(未届)」とするよう申請します。自治体によっては、証明書類の提出を求められる場合があるため、事前に必要書類を確認しておくことをおすすめします。
住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載することで、第三者に対して事実婚関係を証明しやすくなります。ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
(2) 事実婚契約書(内縁契約書)の作成
事実婚の関係性や生活上の取り決めを明文化した契約書を作成することで、第三者に対して関係性を証明しやすくなります。この契約書は、公証役場で公正証書として作成することが可能で、法的な証拠力が高まります。
契約書に記載すべき内容:
- 事実婚関係にあることの確認
- 同居や生活費の分担に関する取り決め
- 財産の管理・分与に関する取り決め
- 万が一の別離時の対応
公正証書として作成することで、証明力が高まり、トラブル防止にも役立ちます。
(3) 自治体のパートナーシップ証明書を取得
一部の自治体では、事実婚や同性カップル向けに「パートナーシップ証明書」を発行しています。この証明書を取得することで、手続きがスムーズになる場合があります。
おわりに
事実婚(内縁関係)のパートナーには、法律上の相続権が認められていません。そのため、大切なパートナーに確実に財産を遺すためには、生前からの適切な対策が必要です。
具体的には、
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 生命保険の受取人指定
などの方法があります。
特に、遺言書を作成することで、法定相続人以外のパートナーへ財産を遺贈する意思を明確に示すことが可能です。また、生命保険の活用により、パートナーに直接的な財産を遺すことも検討できます。早めの対策が、パートナーとの安心した未来を築く第一歩となります。



