介護保険サービスを利用するためには、自治体による「要介護認定」を受ける必要があります。この認定は、高齢者がどの程度の介護や支援を必要としているかを判断するために行われます。

要介護認定 = 「あなたの生活のために介助が必要です」と認めてもらうことです。
この記事では、要介護認定の仕組みや手続きの流れを詳しく解説します。
要介護認定とは?
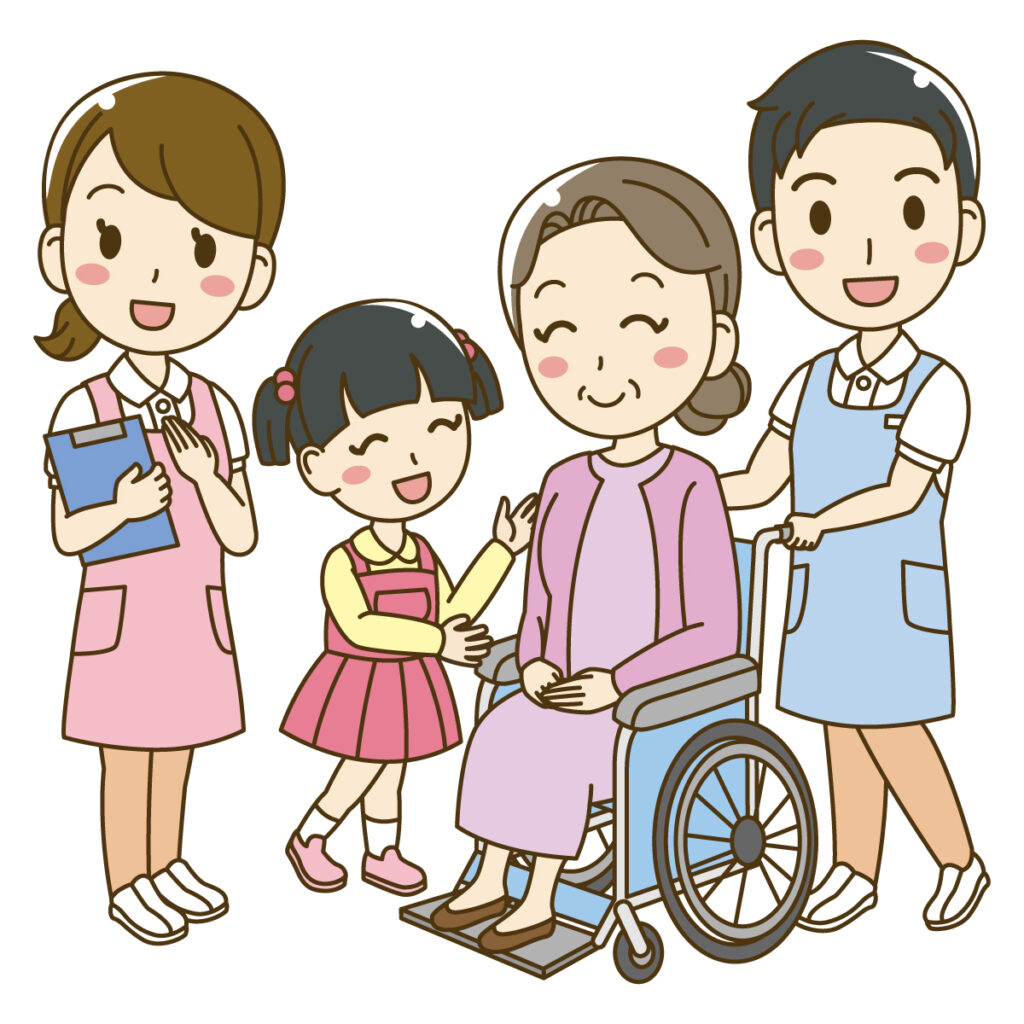
要介護認定は、介護が必要な高齢者に対して、介護サービスを利用できるかどうかを判断する制度です。認定の結果によって、利用できるサービスの種類や内容、上限額が決まります。
認定には以下の2つの状態があります。
- 要支援状態
軽度の支援が必要で、介護予防サービスが効果的とされる状態(例:家事や身支度に一部の支援が必要) - 要介護状態
日常生活全般において、継続的な介助が必要な状態(例:寝たきり、認知症など)
要介護認定の対象者
要介護認定を受ける対象者は以下の通りです。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
- 原因を問わず、要介護・要支援状態となった場合に対象となります。
- 第2号被保険者(40歳~64歳の方)
- 老化に起因する特定疾病(例:末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患など)が原因で要介護・要支援状態となった場合に対象です。
要介護認定の手続きの流れ
要介護認定は、以下の手順で進められます。
1. 申請
介護サービスを利用したい方、またはその家族が、市町村の窓口に要介護認定を申請します。申請書には、本人の状況や希望するサービス内容を記載します。
2. 認定調査
市町村の認定調査員が、申請者の自宅や施設を訪問して心身の状況を調査します。調査では、以下の項目がチェックされます。
- 身体の動き(歩行、着替え、食事など)
- 認知機能(記憶力、判断力など)
- 日常生活動作の支援状況
この調査結果は、コンピュータによる一次判定に用いられます。

認定調査には子どもの立会いが必要です。
親の日常生活の様子や、気になることを事前にメモしておき、調査員に伝えましょう。
3. 主治医意見書の提出
申請者の主治医が、健康状態や介護が必要な理由について意見書を作成します。この意見書は、二次判定で参考資料として使用されます。

申請書にかかりつけの病院名や主治医の氏名を記載する項目があります。
介護を受けたい方の健康状態をよく知る先生、病院を記載しましょう。
4. 一次判定
認定調査の結果をもとに、コンピュータによる要介護認定基準時間の算出が行われます。この基準時間は、介護に必要な時間を示す指標で、要介護度の判定材料となります。
5. 二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による審査が行われます。この審査会で最終的な判定が行われ、要介護度が決定します。
6. 認定結果の通知
審査結果が申請者に通知されます。通知書には、以下の内容が記載されています。
- 要介護度(要支援1・2、要介護1~5)
- 利用できるサービスの内容と上限額
認定結果に不満がある場合、申請者は不服申し立てを行うことも可能です。
要介護度と利用できるサービス
要介護度
要介護度に応じて、利用できるサービスの内容や範囲が異なります。
- 要支援1・2:介護予防を目的とした軽度の支援サービス
- 要介護1~5:介護度に応じた在宅サービスや施設サービス
| 区分 | 特徴・状態例 | 主な支援内容 |
|---|
| 要支援1 | 軽度の支援が必要。家事や買い物で少し手助けが必要な状態。 | 軽い運動や家事支援、生活指導。 |
| 要支援2 | 要支援1よりも少し能力が低下。日常生活の一部で支援が必要。 | 家事支援やリハビリなど継続的な支援。 |
| 要介護1 | 日常生活の一部で介助が必要(例:歩行や排泄)。 | 入浴、トイレなどの一部支援 |
| 要介護2 | 要介護1よりも介助範囲が広がる。 | 入浴・食事・移動などの介助。 |
| 要介護3 | 身体介助が大部分で必要。 | 立ち上がり、歩行、トイレ、衣類の脱着など全面的な介助。 |
| 要介護4 | 常に介護が必要。移動・排泄・食事などの全般的介助。 | 介助無しで日常の生活を行うことが困難。 |
| 要介護5 | 全介助が必要。自力での行動が困難な状態。 | 日常生活全般において介助が必要 |
要介護度が高いほど、利用可能なサービスの範囲が広がり、支給限度額が増えます。
支給限度額
介護保険では、要支援・要介護認定を受けた方が在宅サービスを利用する際、要介護度に応じて1か月あたりの支給限度額が設定されています。
この限度額内でサービスを利用した場合、費用の1割から3割が自己負担となります。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた金額は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 支給限度額(円) |
|---|
| 要支援1 | 約50,320円 |
| 要支援2 | 約105,310円 |
| 要介護1 | 約167,650円 |
| 要介護2 | 約197,050円 |
| 要介護3 | 約270,480円 |
| 要介護4 | 約309,380円 |
| 要介護5 | 約362,170円 |
認定更新と見直し
要介護認定には有効期間があり、期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。また、状態が改善したり悪化したりした場合には、再度認定を受けることが可能です。
おわりに

要介護認定は、介護サービスを適切に利用するための重要な手続きです。
認定を受けることで、利用者は自分の状態に合ったサービスを選択し、必要な支援を受けることが可能になります。
認定の結果に応じて、利用できるサービスや支援内容、費用の負担額が決まるため、申請時には正確な情報を提供することが大切です。
また、認定には一定の手続き期間がかかるため、早めに申請しておくことがスムーズな介護利用につながります。
さらに、状態の変化に応じて認定を更新または見直すこともできるため、定期的にサービスの見直しを行うことが良い介護生活を送るポイントです。


