相続というと、プラスの財産だけをイメージしがちですが、実は借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
もし、被相続人に多額の借金があった場合、自分が抱えきれないほどの借金を抱えてしまうことになる可能性も。
そんな事態を防ぐための制度が「相続放棄」と「限定承認」です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないことを選択する手続きのこと、
限定承認とは、相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済するという制度です。
相続放棄について

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を一切引き継がないことを決定することです。相続放棄を行うと、初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄をするべきケース
- 被相続人に多額の借金がある
- 相続財産の状況が把握できない
- 財産を受け取る意志がない
- 相続人同士の話し合いや手続きが面倒
相続放棄の手続き
相続放棄を希望する場合、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
申述書には、相続人の氏名、被相続人の氏名、相続放棄の理由などを記載します。
相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとされ、相続財産も負債も一切引き継ぎません。
相続放棄に必要な書類
相続放棄には、相続放棄の申述書と関係する戸籍謄本等を提出します。
(1) 相続放棄の申述書
書式記載例(申述人が成人の場合)
書式記載例(申述人が未成年者の場合)(2) 標準的な申立添付書類
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
裁判所 相続の放棄の申述

相続放棄をする人が複数いる場合、戸籍の提出は一度で済みます。

提出した戸籍を返してもらえる「原本還付」という手続きも可能です。提出する前に、裁判所にご相談ください。
関連リンク:裁判所 相続の放棄の申述
相続放棄をすると次順位の相続人に権利が移る
相続放棄を行うと、次順位の相続人が相続権を持つことになります。
例えば、子が全員相続放棄をすると、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人となります。
相続人の範囲と順位
- 配偶者(夫・妻):常に相続します。
- 第一順位:子、(異母兄弟・異父兄弟も相続人)
- 第二順位:親(被相続人に子がいない場合のみ)(両親死亡の場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(両親、祖父母がすでに死亡している場合のみ)
そのため、被相続人(亡くなった人)の借金を相続したくない場合は、順次、子、親、兄弟姉妹が相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄申述の流れ
- 家庭裁判所へ相続放棄の申述をします
相続放棄を行うためには、相続人が被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。
- 家庭裁判所から『照会書』が届きます
申述書を提出すると後日、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。この照会書には、相続の開始を知った日や相続放棄の意思の確認などが質問されます。回答書に記入して家庭裁判所に返送します
- 『相続放棄申述受理通知書』が届きます
回答書を提出し、相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これにより、正式に相続放棄が認められます
限定承認について

限定承認とは、相続人が被相続人の財産と負債を限定して相続する方法です。
これは、相続人が被相続人の負債を相続財産の範囲内で引き受けるもので、相続財産を超える負債は負担しません。
借金の額がどのくらいなのかはっきりしない場合や、プラスの財産がマイナスの財産を上回りそうなら限定承認を検討しましょう。
限定承認の手続き
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述書を提出します。
限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。
家庭裁判所が申述書と提出書類を審査し、限定承認が認められると、相続財産の範囲内で負債を引き受けることが確定します。
関連リンク:裁判所 相続の限定承認の申述
限定承認申述の流れ
- 家庭裁判所に限定承認の申述をします
相続人全員が共同して、家庭裁判所に限定承認の申述を行います。申述の期限は相続の開始を知った日から3か月以内です。
- 裁判所から『照会書』が届きます
申述書を提出すると後日家庭裁判所から「照会書」が送られてきますので記載の上返送します。
- 家庭裁判所の審判。受理されると通知が届きます
- 限定承認の公告(官報に掲載)の手続き・知れたる債権者へ申し出の催告
債務の額と債権者を明らかにするため、官報掲載の手続きをします。また、すでに知っている債権者に対して、申出書等の提出を催告します
- 債権者へ弁済します
- 財産が残った場合は、分割協議
弁済等の手続き後に財産が残った場合は、相続人同士で話し合い財産を分割します。

限定承認は手続きが多く時間がかかります。
弁護士さんや司法書士さんへ依頼することをおすすめします。
3ヶ月以内に判断できない場合は『期間伸長の申立て』
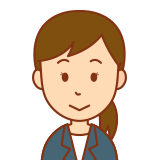
父は会社を経営していました。経営悪化で、あちこちから借り入れをしていたようです。
調べているのですが、3ヶ月以内に間に合わないかも知れません。

家庭裁判所へ期間伸長の申立てをしましょう
もし3ヶ月以内に相続放棄の判断ができない場合、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
伸長が認められる場合
伸長の申立をすれば必ず認められるわけではなく、家庭裁判所の判断により決定します。
主に以下のような状況を判断します。
- 相続財産が複雑・多額
- 相続財産の所在場所・相続人の居住地の遠隔性
- 相続人の能力・健康状態などの状況
単に、手続きや調査をせずに日数が経過してしまった場合や、仕事で時間が取れない、といった理由では、熟慮期間の伸長は認められないことが多いです。
関連リンク:裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書
おわりに
相続放棄と限定承認は、相続人が被相続人の負債を引き継がないようにするための手段です。
相続放棄は一切の相続を放棄するものであり、限定承認は相続財産の範囲内で負債を引き受ける方法です。
相続が発生した場合、これらの手続きについて理解し、必要に応じて適切な選択をすることが重要です。不明点や手続きの詳細については、専門家に相談することをお勧めします。


