深谷市では、性的少数者の人権を尊重し、多様な生き方を支援するために「深谷市パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
この制度は、互いを人生のパートナーとする意思を持つ二人が、市に対して宣誓を行い、その関係を公的に証明するものです。
はじめに


パートナーの代わりに市役所へ必要書類を取りに行きました。でも、「ご本人様の親族ではない」という理由で受け付けてもらえませんでした。
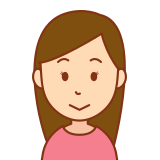
パートナーと一緒に深谷市で暮らすことになりました。
新生活の証に、「婚姻届」のような手続きはないでしょうか?

「パートナーシップ宣誓」という制度をご利用ください。
市役所などの手続きでパートナーの家族と同等の対応を受けることができ、証明書(カード)も発行されます。
近年、多様な生き方が尊重される社会へと変化しています。しかし、同性のパートナーと生活を共にしている方にとって、行政手続きがスムーズに進まないことが少なくありません。
例えば、病院での面会や住民票の続柄の記載、税務関係の証明書取得など、法律上の婚姻関係・親族がないことで手続きが煩雑になるケースが多く見られます。
こうした課題に対応するために、深谷市の「パートナーシップ宣誓制度」を利用しましょう。
行政サービスの一部において、パートナーを「縁故者」として扱うことが可能になり、各種手続きがスムーズに進むようになります。
パートナーシップ宣誓をするメリット

行政手続きがスムーズになる
同性のパートナーと暮らしている場合、法律上の「夫婦」や「親族」ではないため、行政手続きの際に不便を感じることがあります。パートナーシップ宣誓をすると、以下のような行政手続きを円滑に進めることができます。
- 住民票の続柄に「縁故者」と記載可能
- 役所の手続きで関係性を説明する手間が省ける
- 役所の手続きで関係性を説明する手間が省ける
- 税務証明書の取得が可能
- パートナーの住民税や課税証明書、非課税証明書、納税証明書を請求できる
- パートナーの住民税や課税証明書、非課税証明書、納税証明書を請求できる
- 市営住宅の申し込み資格が得られる
- 夫婦や親族向けの市営住宅に同性パートナー同士でも申し込むことが可能
- 夫婦や親族向けの市営住宅に同性パートナー同士でも申し込むことが可能
- 医療・介護に関する行政サービスが受けられる
- パートナーの介護が必要になった際、親族と同様の制度を利用できる場合がある
- パートナーの介護が必要になった際、親族と同様の制度を利用できる場合がある
- 火災や災害時の手続きがスムーズに
- り災証明書の交付申請が可能
- り災証明書の交付申請が可能
- 犯罪被害者遺族見舞金の支給対象になる
- パートナーが犯罪被害に遭った際に、一定の見舞金を受け取ることができる
民間サービスが利用しやすくなる
パートナーシップ宣誓をすることで、民間企業のサービスを家族同様に受けられる場合があります。
- 携帯電話の家族割引が適用される可能性がある
- 住宅ローンの連帯債務者になれる場合がある
- 生命保険の受取人指定がしやすくなる
- 病院での面会・付き添いが認められることがある
ただし、これらの対応は事業者によって異なるため、事前に確認することが必要です。
注意点:法律上の婚姻関係ではない
深谷市パートナーシップ宣誓制度は、法律上の婚姻関係ではなく、相続などの法的な権利や義務は発生しません。
あくまでも深谷市が、双方または一方が性的指向及び性自認に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを証明する制度です。
この制度により、2人に精神的な安心感を与え、日常生活の生きづらさを軽減することを願うとともに、社会全体における性の多様性への理解を深めることを目的としています。
パートナーシップ宣誓の流れ
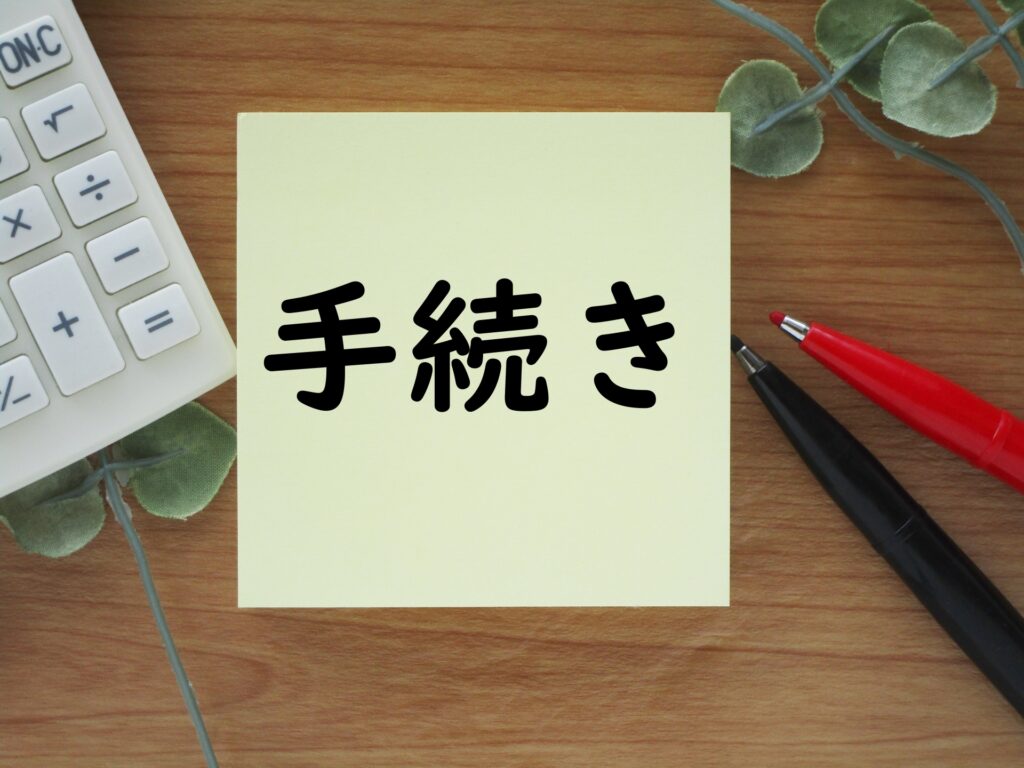
深谷市のパートナーシップ宣誓制度を利用するには、事前予約をした上で、必要書類を用意し、市役所で手続きを行う必要があります。ここでは、宣誓の流れを詳しく解説します。
1. 事前予約
パートナーシップ宣誓を行うには、宣誓を希望する日の7日前までに予約が必要です。以下の方法で予約を行います。
✅ 予約の連絡先
- 電話(深谷市役所 人権政策課:048-574-6643)
- メール(jinken@city.fukaya.saitama.jp)
- 来庁(市役所窓口で直接予約)
💡 ポイント
- 宣誓希望日が既に埋まっている場合があるため、できるだけ早めに予約をすることをおすすめします。
- 予約時に、手続きに必要な書類や持ち物についての説明を受けることができます。
2. 必要書類の準備
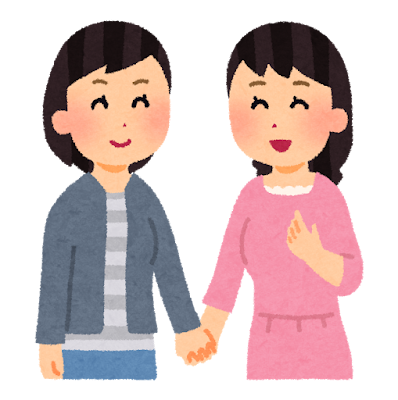
予約が完了したら、宣誓当日までに必要な書類を用意します。書類の不足や不備があると、宣誓が延期になる場合があるため、事前にしっかり準備しましょう。
✅ 必要な書類(すべて発行から3か月以内のもの)
| 書類名 | 内容・取得方法 |
|---|---|
| 住民票の写し | 深谷市に住所があることを確認するために必要(転入予定の方は不要)。 |
| 転入予定住所が確認できる書類(転入予定者のみ) | 賃貸借契約書の写し、転出証明書など。 |
| 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または独身証明書 | 結婚していないことを証明する書類(外国籍の方は婚姻要件具備証明書+日本語訳)。 |
| 本人確認書類(顔写真付きのもの) | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(顔写真なしのものは2点必要)。 |
| 通称使用が確認できる書類(通称を使用する場合) | 社員証、学生証など、通称を日常的に使用していることがわかる資料。 |
💡 ポイント
- 住民票の取得時、本籍やマイナンバーは記載しないように指定する必要があります。
- 書類の不備があると宣誓ができないため、事前にチェックすることが重要です。
3. 市役所での宣誓手続き
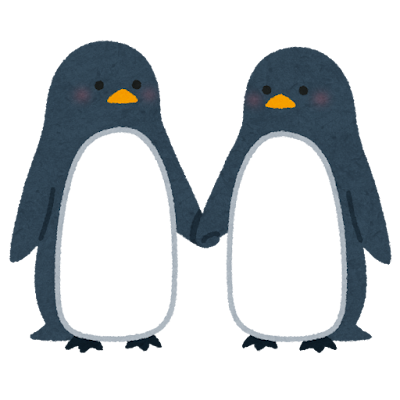
予約した日時に、パートナーと2人そろって市役所へ行きます。以下の流れで手続きを行います。
✅ 宣誓手続きの流れ
- 市役所の窓口で受付を行う
- 事前に予約した日時に、深谷市役所の「人権政策課」へ来庁し、受付を済ませます。
- 個室のスペースが用意されているため、プライバシーが守られた状態で手続きができます。
- 必要書類の確認・本人確認
- 住民票や戸籍抄本、本人確認書類などを提出し、担当職員が内容を確認します。
- 書類に不備があった場合、その場での宣誓はできず、後日改めて予約が必要になることがあります。
- 「パートナーシップ宣誓書」の記入・提出
- 市の担当職員の立ち会いのもと、**「パートナーシップ宣誓書」**を記入し、提出します。
- 自分で記入が難しい場合は、代筆も可能です。
- 手続き完了後、証明書の発行準備へ
- 宣誓手続きが完了すると、市役所で「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」の発行準備が開始されます。
- 証明書の即日発行は原則不可で、交付までに約1週間かかります。
4. 証明書の交付

宣誓後、約1週間後に「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」が交付されます。
✅ 受け取り方法
- 窓口での受け取り
- 本人確認書類を持参し、市役所の窓口で受け取る。
- どちらか1人だけの来庁でも受け取り可能。
- 郵送での受け取り(希望者のみ)
- 事前に送付先を確認し、証明書を郵送してもらうことも可能。
- 郵送費用(簡易書留 470円分)の切手が必要。
💡 即日交付を希望する場合
- 予約時に相談することで、事前に必要書類を提出し、審査を終えておけば即日交付も可能な場合があります。
- ただし、審査の状況によっては即日対応ができないこともあるため、早めの準備が重要です。
5. 宣誓後の手続き

パートナーシップ宣誓をした後に、住所変更や解消などの変更手続きが必要になる場合があります。
✅ パートナーシップ宣誓後の主な手続き
| 手続き内容 | 必要な対応 |
|---|---|
| 証明書の再交付 | 紛失や破損の場合、「再交付申請書」を提出して再発行が可能。 |
| パートナーシップ内容の変更 | 転居などの変更があった場合、「変更届」を提出する。 |
| パートナーシップの解消 | 関係が解消された場合、「返還届」を提出し、証明書を返還する。 |
パートナーシップ宣誓の後は、遺言書の検討を

深谷市のパートナーシップ宣誓制度を利用することで、行政手続きがスムーズになり、日常生活における不便が軽減されます。
しかし、この制度は法律上の婚姻ではないため、相続権が発生しない点には注意が必要です。
もしパートナーが亡くなった場合、法律上の家族ではないため、自動的に遺産を相続することはできません。遺言書がないと、パートナーが築いてきた財産を引き継ぐことが難しくなります。
そのため、パートナーに財産を遺したいと考えている場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。

「遺言」と聞くと、高齢の方が作るものと思われがちですが、遺言書は年齢に関係なく、万が一に備えるための大切な手段です。

遺言は何度でも作り直すことができるため、ライフステージに応じて内容を見直しながら準備しておくと安心です。
具体的な遺言の作成方法や、どのような点に注意すべきかについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
おわりに
深谷市のパートナーシップ宣誓制度は、同性パートナーが行政手続きをスムーズに進めるための制度です。法的な婚姻とは異なり、相続権や税制上の優遇措置などの法的権利・義務は発生しませんが、市役所での手続きや一部の行政サービスを利用しやすくなるメリットがあります。
この制度を活用することで、住民票の続柄を「縁故者」として記載できたり、市営住宅の申し込みが可能になったりするなど、生活の利便性が向上します。また、公的にパートナー関係が証明されることで、社会的な理解を得やすくなるという精神的な安心感も得られます。
パートナーとの生活をより安心で快適なものにするために、パートナーシップ宣誓制度を活用し、将来に向けた準備を進めていきましょう。




