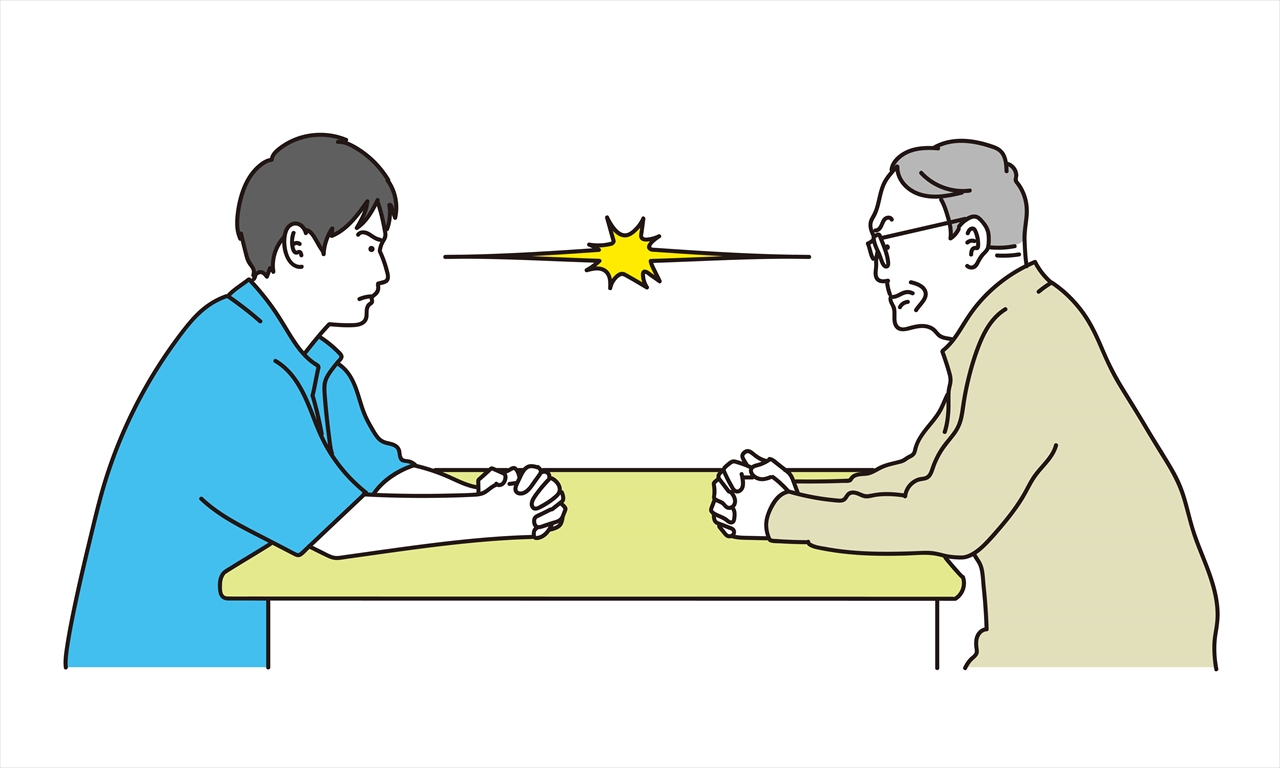長男と仲が悪く、過去に殴られたこともあります。
遺言を書こうと思っていますが、長男には一切遺産を渡したくありません。なにか方法はありますか?

「推定相続人廃除」という裁判所の手続きがあります。検討してみましょう。
推定相続人の廃除とは
まず、『推定相続人』とは、将来、相続が発生したときに財産を受け取る可能性がある人のことです。配偶者、子、直系尊属(親)がこれにあたります。
『推定相続人の廃除』とは、この推定相続人が、被相続人(亡くなる方)に対してひどい虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、法律的に許されない悪い行為をした場合に、その人の相続する権利を奪うことをいいます。
廃除には、2つの方法があります。1つ目は、被相続人がまだ生きている間に家庭裁判所に申し立てて、その相続人を廃除する「生前廃除」です。
2つ目は、被相続人が亡くなった後に、遺言によって指定された遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる「遺言廃除」です。いずれの場合も、家庭裁判所の手続きが必要です。
第892条【推定相続人の廃除】
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第893条【遺言による推定相続人の廃除】
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
相続人廃除の要件・認められた事例
推定相続人廃除の要件
推定相続人が相続の権利を失う(廃除される)理由には、以下のようなケースがあります。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
- 被相続人に対する虐待
被相続人に対して肉体的、精神的にひどい仕打ちをした場合です。例えば、親を暴力で傷つけたり、日常的に嫌がらせをしたりすることが該当します。 - 被相続人に対する重大な侮辱
被相続人に対して、ひどく失礼な態度や言動を繰り返し、相手の尊厳を傷つけた場合です。例えば、親の名誉を傷つける発言をしたり、公の場で恥をかかせたりすることがこれに当たります。 - その他の著しい非行
被相続人やその財産に対して、社会的に許されない重大な迷惑行為をした場合です。例えば、被相続人の許可なくその財産を勝手に担保にしたり、大きな借金を負わせて返済を強要したりすることが含まれます。これにより、被相続人が大きな精神的苦痛や経済的な負担を被った場合などが該当します。
これらの行為が原因となり、推定相続人の相続権が廃除されることがあります。実際の裁判では、これらの行為が複数重なって問題とされることが多く、一つ一つを厳密に分けて判断されるとは限りません。
また、推定相続人の虐待、侮辱、非行の行為について、もし被相続人にも何らかの原因があったり、その行為が一時的なものであった場合には、廃除が認められないこともあります。
例えば、被相続人との間に深刻なトラブルや誤解があったために一時的に感情的になってしまったケースや、被相続人自身の行動が相続人の行為を引き起こす原因となっているような場合です。
こういった状況では、家庭裁判所が相続人の廃除を認めないことがあります。
廃除が認められた例
- 末期がんで自宅療養中の妻に対し、夫が療養に適さない環境を意図的に作り出し、さらに妻の人格を否定するようなひどい言葉を投げかけたなどの夫の行為。このケースでは、家庭裁判所が夫の行為を「虐待」と認定し、相続権の廃除を認める審判を下しました(釧路家庭裁判所北見支部、平成17年1月26日)。
- 学校に通っている間から問題行動を繰り返し、その後、暴力団員と結婚した女性がいました。彼女は、父親が結婚に反対しているにもかかわらず、父親の名前を使って結婚披露宴の招待状を送りました。これにより、父親は大きな精神的苦痛を受け、名誉を傷つけられたとして廃除を認めました。(東京高裁、平成4年12月11日)。
廃除が認められなかった事例
- 夫婦間の相続人廃除が却下された事例。裁判所は廃除を認めるには「婚姻を継続し難い重大な事由」と同程度の非行が必要としました。この事案では、約44年の結婚生活中、夫婦の不和は約5年にすぎず、夫が妻の遺産形成にも貢献していたため、廃除は認められませんでした。結果、初審の廃除の審判が覆され、申立ては却下されました。
- 被相続人Aは、生前に妻Bと長男夫婦と同居していましたが、Bと長男の妻の不和により、口論が絶えませんでした。長男はBに対し暴力的な行動を取り、長男の妻もBに暴力を振るいました。このため、AはBに遺産を相続させ、Bが先に亡くなった場合は長男を除く子どもたちに相続させる遺言を作成し、長男を廃除する遺言を作成しました。しかし、裁判では長男の行動は家庭内の不和によるもので、彼だけに責任があるとは言えず、廃除は認められませんでした。
廃除が認められるのは難しい
推定相続人の廃除は、家庭裁判所による厳格な審査が行われ、その結果として認められるのは非常に難しいケースが多いです。実際に廃除が認められる割合は、申立件数のわずか15~20%程度に過ぎません。
この低い認定率の背景には、相続権を剥奪するという極めて重要な決定が含まれるため、裁判所が慎重に判断する必要があることが挙げられます。単なる不仲や感情的な問題だけでは不十分で、廃除を認めてもらうためには、虐待や重大な侮辱などの客観的な証拠が必要です。また、相続人の行動や背景、被相続人の態度や言動も考慮され、主観的な意見だけでは認められません。
たとえば、暴力や経済的虐待、遺産の無断処分といった行為が廃除の理由に含まれますが、家庭内の複雑な事情や行為の程度なども判断に影響を与えるため、廃除を求める側が確固たる証拠を示すことが重要です。