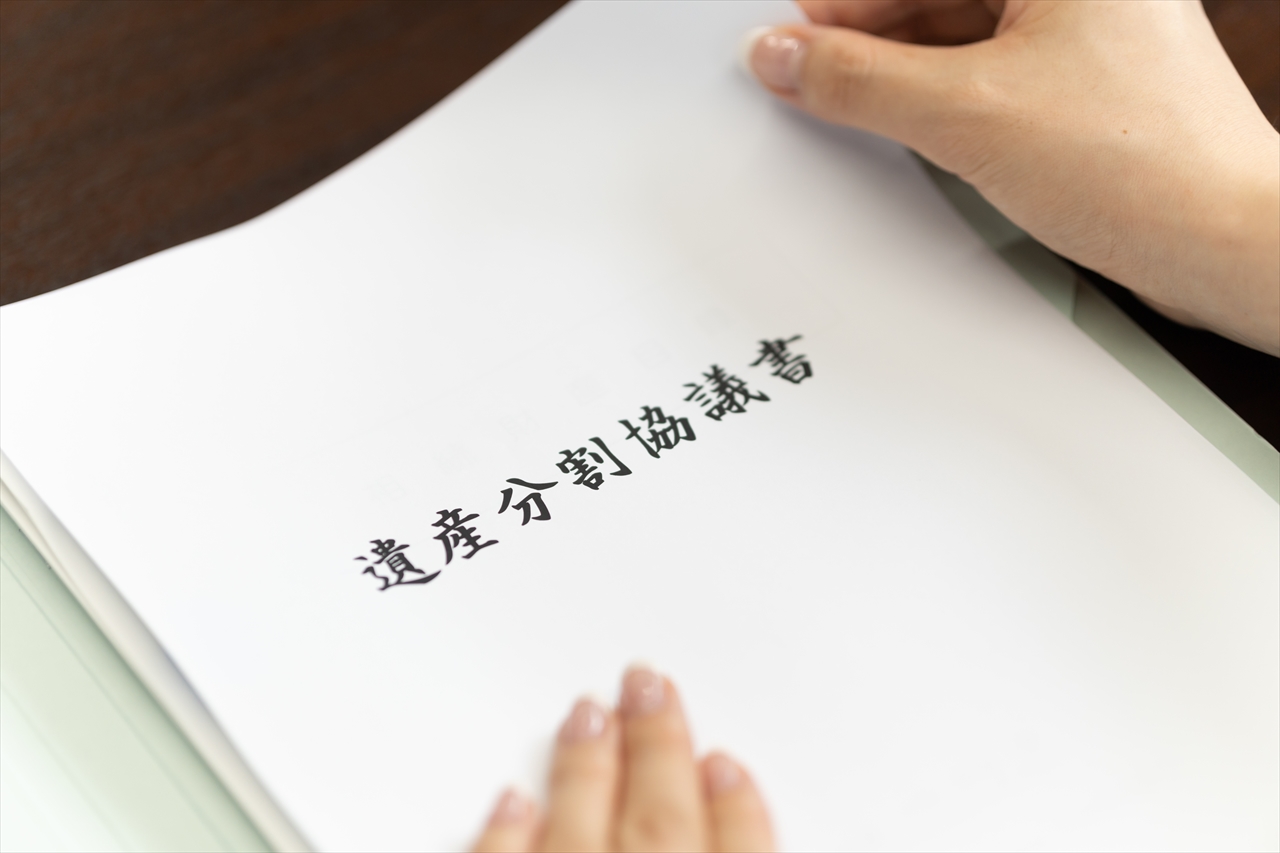遺産分割協議は、亡くなった方の財産を相続人で分割するために重要です。
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産がある場合には、相続人全員が合意する形で遺産の分割方法を決める必要があります。
このプロセスは、家族間の意見の相違が生じることも多く、スムーズに進めるためには事前の知識と準備が欠かせません。
この記事では、
について解説します。
これから遺産分割協議を進めようと考えている方にとって、お役立にたてる情報をご提供できればと思います。
遺産分割協議の基本知識

相続人全員の話し合いで決める
遺産分割協議とは、相続人が亡くなった方の財産をどのように分割するかを話し合いで決める手続きのことです。
民法に相続分の割合が規定されていますが、相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。
協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。
話し合いの結果を書面に残す(遺産分割協議書の作成)
遺産分割協議が無事に終了したら、その内容を正式な書面である遺産分割協議書にまとめる必要があります。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明する重要な書類であり、後々のトラブルを防ぐためにも正確に作成することが求められます。
また、この書類がないと、不動産の登記変更や相続税申告の手続きができません。
遺産分割協議書が必要となる場合
遺産分割協議の重要性
遺産分割協議は、相続人間の意見の相違を解消し、公正な遺産分割を実現するために重要です。合意が得られない場合、法的な手続き(調停や審判)に進むこととなり、時間と費用がかかることがあります。また、適切な手続きを行うことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
相続開始から遺産分割協議のまでの流れ

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、話し合いによって遺産の分割方法を決定するプロセスです。以下に、遺産分割協議の一般的な流れを説明します。
1.遺言書の確認
まず最初に行うべきことは、遺言書があるかどうかを確認することです。遺言書がある場合、その内容に従って財産を分けることになります。
一般的な遺言書は以下のとおりです。
- 手書きの遺言を自宅に保管している(自筆証書遺言)
- 自筆証書遺言を法務局に預けて保管している(自筆証書遺言保管制度)
- 公証役場で遺言を作成している(公正証書遺言)
それぞれの様式で確認方法や手続きの手順が異なります。
以下の記事をご参考ください。
2. 相続人の確定
遺産分割協議を行うためには、まず相続人を確定する必要があります。
相続人の範囲
民法では、法定相続人は亡くなった方の配偶者、子、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹と定められています。配偶者は常に相続人です。
故人に子供がいない場合、次に直系尊属が相続人となります。
相続人の範囲と順位
- 配偶者(夫・妻):常に相続します。
- 第一順位:子、(異母兄弟・異父兄弟も相続人)
- 第二順位:親(被相続人に子がいない場合のみ)(両親死亡の場合は祖父母)
- 第三順位:兄弟姉妹(両親、祖父母がすでに死亡している場合のみ)
以下の記事もご参考ください。
戸籍を取得して相続人を確定します
相続人を確定・証明するために、亡くなった方の死亡時から出生まで遡りすべての戸籍を取得します。
亡くなった方が再婚などをしていた場合、前妻・前夫との間の子供も相続人になります。そのため、亡くなった方が生まれたときの戸籍まで取得し、相続人全員を確認する必要があります。
3. 遺産の調査・確定
相続人が確定したら、次に遺産の内容を確認し、財産目録を作成します。
- 財産目録の作成: 遺産には、不動産、預貯金、株式、動産(車、貴金属など)、負債などが含まれます。これらを全てリストアップし、財産目録を作成します。
- 不動産の確認方法: 市役所の税収課で固定資産税評価証明書(または名寄帳)を取得して不動産の登記事項証明書を取得し、所有者情報や土地・建物の状況を確認します。
- 預貯金の確認方法: 銀行や金融機関に問い合わせ、故人の預貯金口座の残高証明書を取得します。
- 株式やその他の金融資産の確認方法: 証券会社に問い合わせ、保有する株式や投資信託などの残高証明書を取得します。
4.相続放棄・限定承認の検討
借金などの負の遺産が多い場合は、相続放棄または限定承認を検討しましょう。
相続放棄とは、相続人が相続権を放棄することで、その結果、相続財産だけでなく負債も相続しないことになります。
相続放棄と並んで、もう一つの選択肢として存在するのが「限定承認」です。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金など)を弁済するという制度です。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行います。
以下の記事もご参考ください。
5. 遺産分割協議の準備
遺産分割協議を円滑に進めるためには、事前準備が不可欠です。「相続人の確定」、「財産の調査」、「相続放棄・限定承認の検討」といった基本的な手続きを済ませた後に、具体的な遺産分割の協議を開始します。
相続人同士で連絡を取り合い、遺産の分割方法を話し合います。遺産分割は重要かつ込み入った内容になるため、できる限り相続人全員が一堂に会して話し合うことが望ましいです。
しかし、「遠方に住んでいて全員集まるのが難しい」、「他の相続人に任せるから意見はない」、あるいは「他の相続人に会いたくない」といった事情も考えられます。
そのような場合は、全員が一堂に会する必要はありません。メールや電話で意見を伝える、オンライン会議などの方法でも問題ありません。
そして、相続人全員が納得していることを証明するために、遺産分割協議書を作成します。この書類に全員が署名・実印を押印することで、有効な合意となります。
遺産分割協議を円滑に進めるためのポイント

1.全員が情報を共有する
遺産分割協議には、相続人全員の合意が不可欠です。誰か一人でも合意していないと協議自体が無効となり、後の紛争の元になりかねません。
重要なのは、相続人全員が合意し、各相続人の意見が全員に共有されていることです。形式的な会議が行われなくても、全員の意見が反映された合意が得られることが最も重要です。
事情により協議に出席できない相続人がいる場合は、定期的に全員とコミュニケーションを取り協議の進捗を報告しましょう。
「そんな話は聞いていない」、「私に内緒で勝手に話を進めている」といった不信感を持たれないように進めていきましょう。
2.事前準備をしっかりと行う
遺産分割協議の前に、相続財産の内容を正確に把握することが重要です。
不動産や預貯金、株式など、全ての財産をリストアップし、その評価額を確認しておきましょう。
また、各相続人の意向や希望も事前に聞いておくとスムーズです。
相手の立場を尊重する
遺産分割を円滑に進めるためのポイントとして、相手の立場を尊重することが重要です。
例えば、農家を継ぐ相続人がいる場合、農地を売却してしまうと事業が成り立たなくなる可能性があります。
また、生前に近所に住んで身の回りの世話をしていた相続人の貢献度を考慮することも大切です。
各相続人の状況や意向を理解し、協力的な姿勢で話し合いを進めることで、合意に達しやすくなります。
4.隠し事をしない
相続人全員が正確な情報を共有することで、公平な話し合いが可能になります。
例えば、故人の財産や負債に関する情報を隠すことなく公開し、全員が同じ情報を基に協議を行うことが大切です。隠し事があると信頼関係が崩れ、協議が難航する原因となります。
透明性を保ち、オープンな姿勢で話し合うことで、円満な遺産分割が実現します。
5.専門家へ相談する
遺産分割を円滑に進めるためには、専門家に相談することも重要です。
相続人が正しい法的知識を持っていない場合や、地域の慣習などがあり、話し合いに誤解が生じることがあります。
このような状況では、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家から正しい知識を聞くことで、法的手続きを適切に進められます。
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が無事に終了したら、その内容を正式な書面である遺産分割協議書にまとめる必要があります。遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を証明する重要な書類であり、後々のトラブルを防ぐためにも正確に作成することが求められます。
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割方法に合意したことを示す正式な文書です。この書類は相続人全員の署名と押印が必要であり、不動産の登記手続きや金融機関での名義変更手続きなどに使用されます。
遺産分割協議書の雛形・作成例
以下は、遺産分割協議書の例です
遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書の書き方は、法律で定められたルールはありません。
ただし、以下のポイントはおさえて作成しましょう
遺産分割協議書には、以下の内容を含める必要があります。
話し合いで解決しない場合

相続人間で意見が対立し、合意が得られない場合には、以下の方法を検討します。
家庭裁判所へ調停手続を申し立てる
どうしても相続人同士で合意が得られない場合や話し合いに応じない相続人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停委員が中立的な立場で間に入って話し合いを進めるため、公平な解決を目指せます。
- 家庭裁判所の利用: 家庭裁判所に調停を申し立てることで、調停委員という専門の第三者と裁判官が、相続人の意見を元に、解決できる分割方法を検討します。調停は比較的柔軟な手続きであり、相続人間の合意を目指します。
- 調停・審判の流れ: 調停でも合意が得られない場合、家庭裁判所の審判に進むことになります。審判では、裁判官が法的な判断を下し、遺産の分割方法を決定します。
民間の調停機関(ADR機関)もあります。
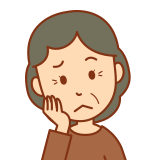
話し合いがまとまらないけど、あまり事を大きくしたくないです。
「裁判所」というと相手にケンカを売ってるみたいで。

民間の調停機関もありますので、利用をご検討ください。
民間調停機関は、裁判外紛争解決手続(ADR)を提供する機関で、相続や離婚などの紛争を中立的な専門家が仲介し、公平かつ迅速に解決を図る場です。裁判所の手続きと比べて、利用時間も柔軟で、忙しい人にも対応しやすいのが特徴です
民間調停機関を利用するメリット
民間の調停機関を利用するメリットは、裁判所での調停に比べて心理的な負担が少なく、手続きが迅速かつ柔軟です。
専門家のサポートを受けながら非公開での話し合いができるため、相続人同士の不安や不信感を軽減し、穏やかな環境で公正な解決を目指すことができます。
特に、裁判所のような公式な場ではなく、リラックスした環境で協議が進められるため、感情的な対立を避けつつ、相続人全員が納得できる合意を得やすくなります。
また、夜間や週末にも対応していることが多く、仕事などで忙しい相続人にとって利用しやすい点も大きなメリットです。
さらに、法務大臣の認証を受けた信頼性の高い機関が多いため、法的な問題にも対応でき、安心して手続きを進めることができます
民間調停機関のデメリット
民間の調停機関を利用する際のデメリットも存在します。まず、民間調停は法的拘束力が弱い場合があり、合意に至ってもその後の履行が確実でないことがあります。
さらに、調停人の質や経験が機関によって異なるため、適切な解決策が見つからない場合もあります 。また、相手方が調停に応じない場合、調停自体が成立しません。
おわりに
遺産分割協議は、故人の遺産を公平に分けるために欠かせない重要な手続きです。
この記事が、相続人の皆様が円滑に協議を進め、公正な遺産分割を実現する一助となれば幸いです。
手続きの過程で不明点や不安が生じた場合は、専門家のアドバイスを積極的に活用してください。
遺産分割協議が無事に完了し、故人、相続人の皆様の意志が尊重される形で相続が行われることを願います。