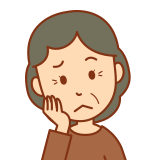
夫の預貯金が思っていたより多く、相続税が掛かりそうです。
いくら位かかるのか心配です。

では、大まかな計算方法を見てみましょう
相続税の計算方法
1.遺産額の合計を算出する
まずは、相続税の計算の出発点となる「正味の遺産額」を求めます。
正味の遺産額とは、相続の対象となるすべての財産から、借金や未払い金などの負債を差し引いた金額です。
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産も相続税の課税対象になります。
また、生命保険金や死亡退職金なども含まれますが、それぞれ法定の非課税枠を超えた部分のみが相続税の対象となります。
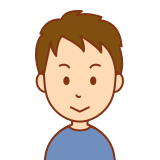
生命保険金も財産に含めるのですか?

はい、生命保険金などは、本来遺産ではなく受取人個人の権利ですが、
相続税の計算では、遺産として計上します。『みなし相続財産』といいます。
でも、全額ではなく以下の金額を超える分だけ、遺産に加えて計算します。
生命保険金等の非課税限度額=500万円✕法定相続人の数
遺産の計算をまとめると以下の通りです。
相続税手続きの遺産の総額=相続・遺贈により取得した財産+みなし相続財産−非課税財産の価格+相続時精算課税の贈与財産の価格−債務及び葬式費用の額+被相続人からの3年以内の贈与額の価格

遺産を取得した人ごとに上記の手順で計算します。
相続人が複数いる場合はその合計額を求めます。
2.基礎控除額を求める
次に、相続税の課税対象となるかどうかを判断するために、「基礎控除額」を計算します。
基礎控除額とは、**相続税がかからない範囲(非課税枠)**のことです。
正味の遺産額がこの基礎控除額を超えている場合に、相続税が発生します。
基礎控除額の計算式は以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
今回のケースでは、法定相続人は「配偶者・長男・長女」の3人ですので、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この4,800万円が基礎控除額となります。
つまり、正味の遺産額がこれを超えるかどうかが、課税の判断基準となります。
3.課税遺産総額を計算する
続いて、相続税の対象となる「課税遺産総額」を計算します。
課税遺産総額とは、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた金額です。
この金額が0円以下であれば、相続税はかかりません。
正味の遺産額を5,300万円とした場合、基礎控除額は4,800万円ですので、
5,300万円 − 4,800万円 = 500万円
この500万円が課税遺産総額となり、この金額に対して相続税が課されることになります。
4.法定相続分を確認する
続いて、相続人それぞれの法定相続分を確認します。
法定相続分とは、民法によって定められている遺産分割の目安となる割合のことです。
「配偶者・長男・長女」の3人が法定相続人の場合。
この場合の法定相続分は、次のようになります。
- 配偶者:1/2(全体の50%)
- 長男 :1/4(残り1/2を2人で分けたうちの1人)
- 長女 :1/4(同上)
5.課税遺産総額を法定相続分で分けた場合の取得金額を計算する
次に、ステップ3で求めた課税遺産総額500万円を、ステップ4で確認した法定相続分に基づいて分割したと仮定し、各相続人が相続したとみなされる金額を算出します。
被相続人Aさんの家族構成(配偶者・長男・長女)の場合、法定相続分に応じた課税対象額は以下の通りです。
- 配偶者:500万円 × 1/2 = 250万円
- 長男 :500万円 × 1/4 = 125万円
- 長女 :500万円 × 1/4 = 125万円
この金額をもとに、それぞれの相続税額を次のステップで計算していきます。
6.各法定相続人の取得金額に対する相続税額の計算
各相続人の取得金額に対して、以下の速算表を用いて相続税額を計算します:
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
今回のケースでの取得金額は以下の通りです:
- 配偶者:250万円 → 税率10%、控除額0円
- 長男 :125万円 → 税率10%、控除額0円
- 長女 :125万円 → 税率10%、控除額0円
7.相続税額を計算する
速算表に基づいて、各相続人の相続税額を計算します。
配偶者:250万円 × 10% - 0円 = 25万円
長男 :125万円 × 10% - 0円 = 12万5,000円
長女 :125万円 × 10% - 0円 = 12万5,000円
8.実際の相続割合に基づいて各人の納税額を計算する(配偶者の税額軽減を考慮)
最後に、実際の相続割合をもとに、それぞれの納税額を算出します。
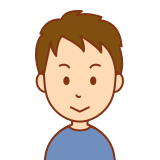
預貯金5,000万円は、母の老後の資金として母が相続、土地と建物は長男の私が引き継ぐことになりました。
遺産の分割を以下のようにしたとします:
- 配偶者:5,000万円(預貯金等)
- 長男 :300万円(不動産価格)
- 長女 :0円(相続なし)
相続財産の総額は5,300万円のため、実際の取得割合は次のようになります:
- 配偶者:5,000万円 ÷ 5,300万円 ≒ 94.34%
- 長男 :300万円 ÷ 5,300万円 ≒ 5.66%
- 長女 :0%
この割合をもとに、相続税50万円を按分すると次のようになります:
- 配偶者:50万円 × 94.34% ≒ 47万1,700円
- 長男 :50万円 × 5.66% ≒ 2万8,300円
- 長女 :0円
▶ 配偶者の税額軽減を適用した後の最終納税額
配偶者については「配偶者の税額軽減」が適用され、相続税は全額免除されます。したがって、配偶者の課税額(47万1,700円)はすべて控除されます。
その結果、最終的な相続税の納税額は以下の通りです:
- 配偶者:0円(税額軽減により免除)
- 長男 :2万8,300円
- 長女 :0円(相続なし)
配偶者が全額相続すると「二次相続」で相続税が高額になることも
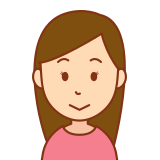
「配偶者の税額軽減」があるなら、母が全部相続すれば相続税はかからないのでお得ですね。

でも、いずれお母様が亡くなられたときの相続で、相続税が高額になってしまうこともあります。
相続税には、「配偶者の税額軽減」という大きな特例があります。
これは、配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い方まで相続税がかからないという制度です。
たとえば、今回のケース(遺産総額5,300万円)で、配偶者がすべての財産を相続すれば、相続税は一切発生しません。
しかし注意すべきはその後。
配偶者が亡くなったときに再び相続が発生します。これが「二次相続」です。
一次相続で財産をすべて配偶者に集約した場合、二次相続では相続人の人数が減るため控除額が下がります。
また、今度は配偶者の税額軽減が使えないため、相続税が大きくなる可能性があります。
相続人 子2人が5,300万円を相続した場合
■ 相続人:子ども2人
→ 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
■ 遺産総額:5,300万円
→ 課税遺産総額:5,300万円 − 4,200万円=1,100万円
■ 法定相続分による課税額
子①:550万円
子②:550万円
■ 税率(速算表より)
1,000万円以下:10%、控除額0円
■ 各人の相続税
550万円 × 10% = 55万円
→ 相続税合計:110万円
相続税に関する相談
相続税の計算や手続きは非常に複雑です。
今回ご紹介した事例のようにほぼ現金の場合は比較的わかりやすいですが、資産価値の判断、計算が難しい財産もあります。(借地権、非上場株式など)
不明な点がある場合は、税務署などの相談窓口や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、相続財産が多岐にわたる場合や、遺産分割に関してトラブルが予想される場合には、早めに専門家に相談して適切な対策を講じましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国税に関する相談 |
機関名:熊谷税務署 所在地:〒360-8620 埼玉県熊谷市仲町41番地 電話番号:048-521-2905 詳細情報:熊谷税務署 |
| 税理士による無料相談 |
団体名:関東信越税理士会熊谷支部 所在地:〒360-0012 埼玉県熊谷市宮町2-144 コーポビアネーズ203号 電話番号:048-521-3312 詳細情報:関東信越税理士会熊谷支部 |

税務署には、電話相談の専用ダイヤルがあります。
相続税について電話で質問する場合は以下に問い合わせましょう。
国税電話相談センター
0570-00-5901(ナビダイヤル)
受付時間は、8時30分~17時00分(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)
個別の面談による相談をご希望の場合は、税務署へ予約が必要です。

